同棲で必要な転入届の手続きガイド|期限・書類・世帯の決め方をわかりやすく解説

「同棲を始めるときの転入届って、どうやって手続きすればいいんだろう……」
そんな疑問を抱えているカップルも多いのではないでしょうか。 同棲は新しい生活のスタートですが、住民票の手続きや世帯主の決め方など、わからないことだらけで不安になりますよね。
この記事では、同棲時の転入届の手続き方法から必要書類、世帯主の決め方まで詳しく解説していきます。 スムーズに新生活を始められるよう、手続きのポイントをしっかりマスターしていきましょう!
転入届はいつまでに出す?期限と手続きの流れをチェック
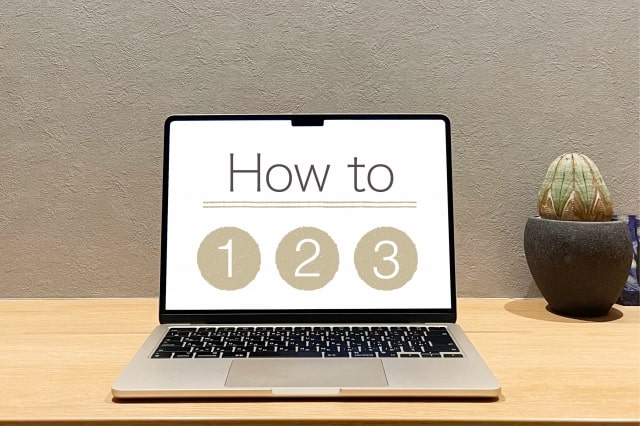
同棲を始める際の転入届には、しっかりとした期限が設けられています。 まずは基本的なルールと手続きの流れを確認していきましょう!
転入届の提出期限(14日以内)の基本ルール
転入届の提出期限は、引越した日から14日以内です。
この期限は住民基本台帳法によって定められており、正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。 そのため、同棲を開始したら速やかに手続きを済ませることが重要です。
なお、14日を過ぎても届出は可能ですが、一定期間経過すると窓口で状況確認や疎明資料等を求められる場合があります。 余計な手間を避けるためにも、期限内の手続きを心がけましょう。
マイナンバーカードの住所変更は90日以内
転入届と併せて重要なのが、マイナンバーカードの住所変更手続きです。
転入届の提出後、マイナンバーカードの住所変更手続きが行われないまま90日が経過すると、マイナンバーカードが失効してしまいます。 失効した場合の再発行は有料(1,000円)となるため、転入届と同時に手続きを済ませておくことをおすすめします。
また、住所変更により署名用電子証明書は自動的に失効するため、e-Taxなどを利用している方は再発行が必要です。
同市区町村内と他市区町村間の手続きの違い
引越先によって必要な手続きが異なります。
他市区町村への引越の場合
- 旧住所の役所で「転出届」を提出→「転出証明書」を受領
- 新住所の役所で「転入届」を提出(引越日から14日以内)
同一市区町村内での引越の場合
- 「転居届」のみを提出(転出届・転入届は不要)
同棲カップルの多くは他市区町村間の引越になるため、転出・転入の両方の手続きが必要になります。 事前に転出届を済ませておけば、引越後の手続きがスムーズに進められるでしょう。
転入届に必要な書類と持ち物一覧【忘れ物ゼロチェックリスト】

転入届の手続きには、いくつかの書類が必要です。 ケース別に必要な書類をまとめていきますので、事前にしっかり準備しておきましょう!
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
すべてのケースで必要となるのが本人確認書類です。
マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等のいずれかを持参してください。 複数あれば、より確実に本人確認ができます。
マイナンバーカードを持参する場合は、転入届と同時に住所変更手続きも済ませられるため一石二鳥です。 暗証番号(4桁の数字)も忘れずに確認しておきましょう。
転出証明書が必要なケース/不要なケース
転出証明書が必要なケース
- 通常の転出届で手続きした場合
- 窓口で転出届を提出した場合
転出証明書が不要なケース
- マイナンバーカード・住基カードで転出手続きした場合
- オンライン(マイナポータル)で転出届を提出した場合
マイナンバーカードを使った特例転出の場合、転出証明書の代わりにマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要になります。 転出方法によって持参するものが変わるため、事前に確認しておくことが大切です。
印鑑・委任状など追加で必要になることがある書類
その他、状況に応じて以下の書類が必要になる場合があります。
印鑑 自治体によっては印鑑が必要な場合があります。 念のため持参しておくと安心でしょう。
委任状 代理人が手続きを行う場合、本人または世帯主からの委任状が必要です。 ただし、同一世帯の家族であれば委任状なしで手続きできます。
外国人の方 在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。 カードの裏面に新住所を記載してもらえます。
ケース別:同市内/他市区町村/代理人による手続き
他市区町村からの転入(一般的なケース)
- 転出証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 印鑑(自治体による)
- 外国人の方:在留カードまたは特別永住者証明書
マイナンバーカード利用の場合
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
- 暗証番号(4桁)の確認
代理人による手続き
- 上記書類に加えて
- 委任状(任意代理人の場合)
- 代理人の本人確認書類
書類の不備があると手続きができないため、事前に転入先の自治体ホームページで確認しておくことをおすすめします。
同棲ならではの世帯パターンとメリット・デメリット
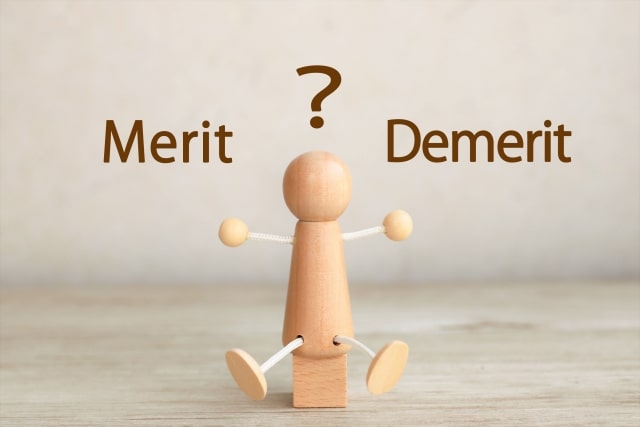
同棲カップルが転入届を提出する際、世帯主をどのように設定するかが重要なポイントです。 それぞれのパターンのメリット・デメリットを理解して、最適な選択をしていきましょう!
一方が世帯主で、もう一方が「同居人」になる場合
一方を「世帯主」、もう一方を「同居人」とするパターンです。
このパターンでは、2人で1つの住民票を作成します。 「同居人」とすることで健康保険や公的年金の扶養対象にできる可能性があり、経済的なメリットが期待できます。
ただし注意点もあります。 住民票にその旨が記載されるため、引越しの際に住民票の提出が求められる企業で働いている場合、同棲をしていることが会社に知られてしまうリスクがあります。
また、同棲解消となった場合、世帯主だった方の引越し先が同一の市区町村内だと、住民票に相手の名前が残ってしまうという点も考慮が必要です。
「夫(未届)・妻(未届)」として登録する場合
住民票に記入できる恋人の続柄は、「夫(未届)」「妻(未届)」のパターンもあります。
この登録方法では、2人の関係を事実婚=”内縁”関係とすることができ、内縁関係が認められることで、社会保険で片方の扶養に入ることが可能になるケースもあります。
事実婚の配偶者が遺族年金を受給する際には、住民票の記載が重要になるため、将来的な結婚を考えているカップルには有効な選択肢でしょう。
二人とも別世帯(世帯分離)のままにする場合
それぞれが世帯主として住民登録をする(住民票を分ける)ことも可能です。
このパターンでは、同じ住所に住んでいても、それぞれが独立した世帯主となります。 双方とも別々に住民票を作成し、自分を世帯主として登録するため、完全にプライバシーが保たれます。
それぞれのメリット・デメリット比較
一方が世帯主、もう一方が同居人
- メリット:扶養に入れる可能性、手続きの簡素化
- デメリット:会社に同棲がバレる、解消時に名前が残る可能性
夫(未届)・妻(未届)として登録
- メリット:内縁関係として認められやすい、社会保険の扶養対象
- デメリット:会社に関係性がバレる
二人とも世帯主
- メリット:プライバシーを守れる、住民票の情報から同居人の有無を知られずに済む
- デメリット:扶養関係は築けない、それぞれ手続きが必要
どのパターンを選ぶかは、収入状況や会社の制度、将来の関係性などを総合的に考慮して決めることが大切です。
住民票の続柄はどうなる?同居人か未届の夫・妻かの違い

住民票の続柄表記は、同棲カップルにとって重要な要素です。 自治体による違いや選択のポイントを詳しく見ていきましょう!
自治体によって異なる続柄の表記ルール
住民票の続柄について、大阪市のホームページでは「内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが、準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ扱い」を受けていると記載されています。
しかし、続柄の表記方法は自治体によって若干の違いがあります。 転入届を提出する際は、窓口で具体的な表記方法について確認しておくことをおすすめします。
「同居人」と「未届の夫・妻」の違いと選び方
「同居人」として登録する場合 単純に同じ住所に住んでいる人という位置づけです。 特別な関係性を示すものではないため、友人同士のルームシェアでも使用される表記になります。
「未届の夫・妻」として登録する場合 事実婚であることを証明する書類として住民票が活用できます。 日本年金機構が事実婚を判断する書類としては、住民票が一番に挙げられているため、将来的に事実婚としての権利を主張したい場合に有効です。
選択の基準は以下のとおりです:
- 単純な同棲関係:「同居人」
- 事実婚として認めてもらいたい:「未届の夫・妻」
- 将来の結婚を前提とした関係:「未届の夫・妻」
同性カップルやパートナーシップ制度への対応
近年、自治体によってはパートナーシップ制度が整備されています。 同性カップルの場合でも、制度を利用していれば住民票に適切な続柄を記載できる可能性があります。
詳細は各自治体の制度を確認し、窓口で相談してみることが大切です。 時代の変化とともに、より多様な関係性に対応した制度が整備されつつあります。
オンライン手続きと窓口手続きの違い|引越しワンストップの実態
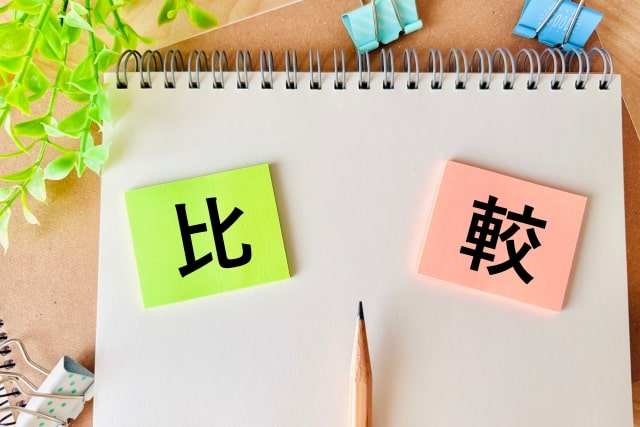
転入届の手続きには、オンラインと窓口それぞれの特徴があります。 効率的に手続きを進めるため、それぞれの違いを理解しておきましょう!
マイナポータルでできること(転出届のオンライン申請)
マイナポータルを利用すれば、全ての市区町村で転出届の提出がオンラインで申請可能です。
2023年2月から開始された「引越しワンストップサービス」により、マイナンバーカードがあれば自宅からでも転出届が提出できるようになりました。 これにより、転出元の役所に足を運ぶ手間が省けます。
オンライン転出届の利用条件は以下のとおりです:
- マイナンバーカードを持っている
- マイナポータルにアクセスできる環境がある
- 転出予定日より14日前または新しい住所に住み始めてから14日以内
窓口に行かないとできないこと(転入届・本人確認)
一方で、転入届は必ず窓口での手続きが必要です。
転入届、転居届についてはオンラインで来庁予定連絡をした上で、窓口での手続きが必要となっています。 これは本人確認や書類の原本確認が必要なためです。
窓口でしかできない手続き:
- 転入届の提出
- マイナンバーカードの住所変更(継続利用手続き)
- 印鑑登録
- 国民健康保険の加入手続き
事前予約や混雑を避けるコツ
窓口での手続きを効率化するためのポイントをご紹介します。
来庁予約の活用 多くの自治体で、転入(転居)届提出のための来庁予約が可能です。 予約をしておくことで、待ち時間を短縮できます。
混雑を避ける時間帯
- 平日の午前中(開庁直後を除く)
- 平日の午後2時~4時頃
- 月末・月初を避ける
必要書類の事前準備
- 自治体ホームページで必要書類を確認
- 書類の不備を避けるため、事前に電話で問い合わせ
- 記入例をダウンロードして事前記入
効率的な手続きにより、同棲生活のスタートをスムーズに切れるでしょう。
転入届後に必要なその他の住所変更手続きまとめ

転入届の提出後も、さまざまな住所変更手続きが必要です。 漏れのないよう、主要な手続きをチェックしていきましょう!
運転免許証の住所変更
運転免許証の住所変更は、マイナンバーカード、住民票、新しい住所が記載された保険証など、住所を確認する証明書類が必要です。
手続き場所:
- 新住所を管轄する警察署
- 運転免許センター
- 警察署の交通課
必要書類:
- 運転免許証
- 住所を証明する書類(住民票、マイナンバーカードなど)
- 申請用写真(他都道府県からの転入の場合)
手続きは転入届と同時に済ませておくと、金融機関などの住所変更がスムーズになります。
郵便物の転送届
旧住所宛の郵便物を新住所に転送してもらうための手続きです。
手続き方法:
- 郵便局窓口
- インターネット(e転居)
- ポスト投函
転送期間は1年間無料で、同棲を始める前に手続きしておくことをおすすめします。 重要な書類や荷物の受け取り漏れを防げるでしょう。
銀行口座・クレジットカードの住所変更
金融機関の住所変更も忘れずに行いましょう。
銀行口座
- インターネットバンキング
- 郵送
- 窓口
クレジットカード
- インターネット
- 電話
- 郵送
住所変更を怠ると、重要な通知が届かなくなる可能性があります。 特に税務関連の書類は、正確な住所に送付される必要があるため注意が必要です。
勤務先・健康保険・税金関係の手続き
勤務先への届出
- 住所変更届の提出
- 通勤手当の見直し
- 住宅手当の申請・変更
健康保険
- 国民健康保険:転入先で新規加入
- 社会保険:勤務先に住所変更届
税金関係
- 住民税:自動的に新住所に変更
- 所得税:確定申告は新住所の管轄税務署
これらの手続きを計画的に進めることで、新生活における各種サービスを滞りなく利用できるようになります。
まとめ

同棲における転入届の手続きは、引越日から14日以内に完了させることが法律で定められています。 マイナンバーカードの住所変更も90日以内に済ませなければ失効してしまうため、転入届と同時に手続きを行うことが重要です。
世帯主の決め方については、それぞれの生活スタイルや将来の計画に応じて選択してください。 扶養関係を築きたい場合は一方を世帯主とし、プライバシーを重視する場合は二人とも世帯主にするという選択肢があります。
転入届後は運転免許証や金融機関の住所変更など、様々な手続きが必要になります。 リストを作成して計画的に進めることで、スムーズに新生活をスタートできるでしょう。
同棲は人生の大きな節目です。 手続きを確実に済ませて、素敵な新生活を始めてくださいね!