同棲カップルの入居審査は年収で決まる?通過の目安と不安を解消するポイント
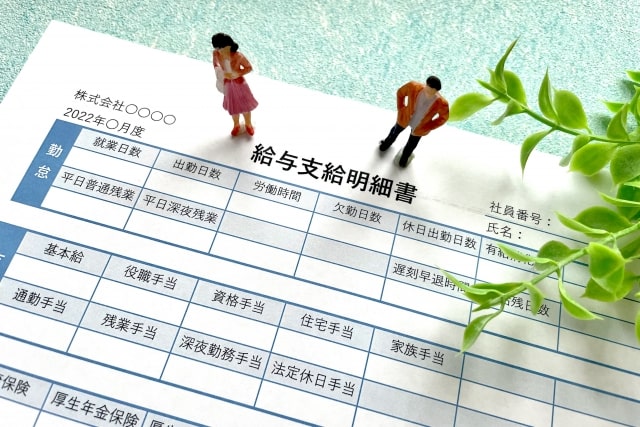
「同棲を始めたいけど、入居審査に通るか心配……」
そんな不安を抱えているカップルは多いのではないでしょうか。
同棲カップルの入居審査では、年収や雇用形態、契約者をどちらにするかなど、単身者とは異なるポイントがいくつも存在しています。しかし、事前に審査の仕組みや対策を知っておけば、スムーズに理想の物件を見つけることも十分可能です。
この記事では、同棲カップルが入居審査を通過するための年収目安や具体的な対策、さらには将来を見据えた契約時の注意点まで詳しくお伝えしていきます。安心して新生活をスタートできるよう、しっかりとポイントを押さえていきましょう!
同棲カップルの入居審査はどう見られる?基本の仕組みを解説
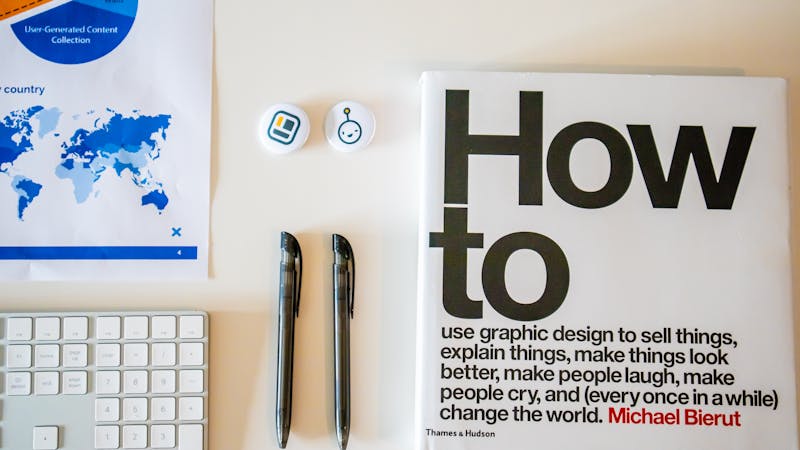
まず理解しておきたいのが、同棲カップルの入居審査における基本的な仕組みについてです。
一般的に、賃貸物件の入居審査では「安定した家賃支払い能力があるか」「物件や近隣住民に迷惑をかけないか」といった点が重視されます。しかし、同棲カップルの場合は単身者と比べて、いくつかの特徴的な審査ポイントが存在しているのが現実です。
契約名義人の収入が審査の中心になる理由
同棲カップルが賃貸物件を借りる際、基本的には「どちらか一方が契約名義人」となるケースが一般的です。
なぜなら、賃貸借契約は法的には「個人と大家(管理会社)との契約」だからです。つまり、契約名義人となった方の年収や信用情報が、審査の中心的な判断材料となります。
たとえば、年収300万円のAさんと年収500万円のBさんが同棲する場合、Bさんを契約名義人にした方が審査には有利になります。ただし、一部の物件や管理会社では、同居人となる方の収入も参考情報として確認されることもあるので注意が必要です。
同棲カップルが「厳しく見られやすい」と言われる背景
残念ながら、同棲カップルは単身者や夫婦と比べて「審査が厳しくなりがち」というのが不動産業界の傾向です。
その主な理由として、以下のような大家側の懸念が挙げられます。まず「関係が破綻した際の家賃滞納リスク」があること。さらに「騒音トラブルが起きやすい」という先入観。そして「短期間で退去する可能性が高い」という判断などです。
しかし、これらはあくまで一般的な傾向であり、適切な対策を取ることで審査通過の可能性を高めることは十分できます。むしろ「二人の収入があることで支払い能力が安定している」という見方をしてくれる大家さんも少なくありません。
家賃と年収の関係|審査に通る目安は「月収の3倍・年収36倍」

入居審査において最も重要な判断基準となるのが、家賃と年収のバランスです。
一般的に「家賃は月収の3分の1以内」「年収の36分の1以内」が適正とされており、この基準を上回る物件は審査が厳しくなる傾向があります。同棲カップルの場合でも、この基本的な考え方は変わりません。
家賃と年収のバランスを計算する方法
具体的な計算方法は非常にシンプルです。
月収ベースで考える場合は「月収 ÷ 3 = 適正家賃」、年収ベースなら「年収 ÷ 36 = 適正家賃」で算出できます。たとえば月収30万円の方なら10万円、年収400万円なら約11万円が家賃の目安となるわけです。
ただし、この計算はあくまで「審査に通りやすい目安」であり、絶対的な基準ではありません。実際には、勤務先の安定性や勤続年数、貯蓄状況なども総合的に判断されるためです。
手取りと総支給、どちらが基準になるのか?
多くの方が迷うポイントが「手取り金額と総支給額のどちらで計算すべきか」という点でしょう。
基本的に、入居審査では「総支給額(額面)」が判断基準となります。これは、収入証明書や源泉徴収票に記載されているのが総支給額だからです。
しかし、実際の生活を考える際には「手取り金額の3分の1」で物件を探すことをおすすめします。なぜなら、総支給額で計算してしまうと、実際の支払い能力を超えた家賃設定になってしまう可能性があるからです。
家賃別・年収目安の早見表
参考として、家賃別の年収目安をまとめた表をご紹介します。
| 家賃 | 必要年収(目安) | 必要月収(目安) |
|---|---|---|
| 7万円 | 252万円以上 | 21万円以上 |
| 8万円 | 288万円以上 | 24万円以上 |
| 9万円 | 324万円以上 | 27万円以上 |
| 10万円 | 360万円以上 | 30万円以上 |
| 12万円 | 432万円以上 | 36万円以上 |
| 15万円 | 540万円以上 | 45万円以上 |
このように、希望する家賃に応じて必要な年収も明確になります。ただし、これらは一般的な目安であり、物件や管理会社によって基準は異なることも覚えておいてください。
二人の収入は合算できる?連名契約や保証人制度の実態

同棲カップルにとって重要なのが「二人の収入を合わせて審査してもらえるか」という点です。
実は、この点については物件や管理会社によって対応が大きく分かれています。収入合算が可能な場合もあれば、契約名義人の収入のみで判断される場合もあるのが現実です。
収入合算が認められるケース(連名契約・保証人あり)
収入合算が認められやすいのは、以下のようなケースです。
まず「連名契約」が可能な物件の場合。これは、カップル両方が契約者となり、連帯して家賃支払い義務を負う契約形態です。また「一方が保証人になる形での契約」も収入合算が認められやすくなります。
さらに、個人大家さんが管理している物件では、交渉次第で収入合算を認めてもらえることも少なくありません。特に、長期居住を前提とした場合や、二人の関係が安定していることをアピールできれば、柔軟に対応してもらえる可能性が高まります。
収入合算ができないケース(大手管理会社の場合)
一方で、収入合算が難しいのは大手管理会社が運営する物件です。
大手では審査基準が画一的に決められていることが多く、「契約名義人の収入のみ」で判断されるケースが一般的となっています。このような場合は、より収入が高い方を契約名義人にすることが重要になってきます。
ただし、同居人の収入も「参考情報」として提出を求められることがあります。これは、世帯全体の支払い能力を確認するためで、審査にプラスに働くことも多いため、積極的に提出することをおすすめします。
契約者をどちらにするか迷った時の判断基準
契約者をどちらにするか迷った場合の判断基準をお伝えしていきます。
最優先すべきは「年収の高さ」です。次に「勤務先の安定性」、そして「勤続年数の長さ」を考慮しましょう。また「信用情報に問題がないか」も重要な判断材料となります。
たとえば、年収は同程度でも一方が正社員、もう一方が契約社員という場合は、正社員の方を契約名義人にした方が審査には有利です。このように、総合的な判断が必要になることを理解しておいてください。
年収に不安がある場合の突破法|転職直後・非正規・フリーランスのケース別対策

年収や雇用形態に不安がある場合でも、適切な対策を取ることで入居審査を突破することは可能です。
重要なのは、自分たちの状況に応じた適切な書類や資料を準備することです。ここからは、よくあるケース別に具体的な対策をお話ししていきます。
転職直後や試用期間中に有効な書類(内定通知・雇用契約書)
転職直後や試用期間中の方は、通常の収入証明書類が用意できないケースが多いでしょう。
そんな時に有効なのが「内定通知書」や「雇用契約書」です。これらの書類には予定年収が記載されているため、将来の支払い能力を証明する材料として活用できます。
さらに「前職の源泉徴収票」も併せて提出することで、過去の収入実績をアピールすることが可能です。また、転職理由が「キャリアアップ」や「年収アップ」である場合は、その旨を説明することで印象を良くすることもできます。
派遣・契約社員が審査を通すコツ
派遣社員や契約社員の方は、雇用の安定性が懸念されやすいのが現実です。
しかし、以下のような対策を取ることで審査通過の可能性を高められます。まず「長期契約であることをアピール」する。次に「派遣会社での勤続実績を強調」する。そして「専門性の高いスキルを持っていることを伝える」ことも効果的です。
また、派遣会社によっては「就業証明書」を発行してくれる場合があります。この書類には契約期間や時給、月収見込みなどが記載されているため、収入証明として活用することができるでしょう。
フリーランス・個人事業主は確定申告や入金履歴を活用
フリーランスや個人事業主の方は、収入の安定性を証明するのが最大の課題となります。
そこで重要になるのが「確定申告書」の活用です。できれば過去2〜3年分を用意し、安定した収入があることをアピールしましょう。また「主要クライアントとの契約書」や「継続的な入金履歴」も有効な証明資料となります。
さらに「売上予測書」や「事業計画書」を作成して提出することで、将来的な収入見通しを示すことも可能です。ただし、これらの書類は物件によって受け入れてもらえない場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。
貯金や残高証明が有効に働くケース
年収に不安がある場合、貯蓄状況を示すことで審査を有利に進められることがあります。
特に「家賃の24ヶ月分以上の貯蓄」がある場合は、大きなプラス要素となります。なぜなら、万が一収入が途絶えても、一定期間は家賃を支払い続けられることが証明できるからです。
預金残高証明書は銀行で有料で発行してもらえるため、審査に不安がある場合は積極的に活用してみてください。ただし、残高証明書には有効期限があるので、発行時期には注意が必要です。
審査落ちを避けるために押さえておきたい書類とチェックリスト

入居審査をスムーズに進めるためには、必要書類の準備が欠かせません。
書類不備による審査の遅延や、最悪の場合は審査落ちを避けるためにも、事前にしっかりとチェックリストを作成しておくことが大切です。
必須書類(身分証明書・収入証明など)
まず、どの物件でも必ず求められる基本的な書類について整理していきましょう。
身分証明書としては「運転免許証」または「健康保険証+住民票」が一般的です。収入証明については「源泉徴収票」「給与明細書(直近3ヶ月分)」「課税証明書」のいずれかが必要となります。
また、勤務先を証明する「在籍証明書」や「雇用契約書」も求められることが多いでしょう。さらに、緊急連絡先として「保証人の身分証明書」や「保証人の収入証明」も必要になる場合があります。
追加提出で信頼度を上げる書類(源泉徴収票・預金残高証明など)
必須書類以外にも、審査を有利に進めるために任意で提出できる書類があります。
たとえば「過去複数年の源泉徴収票」で収入の安定性をアピールしたり、「預金残高証明書」で支払い能力の高さを示したりすることが可能です。また「勤続年数を証明する書類」や「資格証明書」なども、信頼性向上に役立ちます。
同棲カップルの場合は「両者の関係性を示す書類」として、同じ住所の住民票や共通の保険証などを提出することで、関係の安定性をアピールできることもあります。
書類提出でやりがちなNG例
書類提出時によくある失敗例も知っておきましょう。
最も多いのが「書類の有効期限切れ」です。住民票や課税証明書には発行から3ヶ月という有効期限があるため、古いものを使い回さないよう注意が必要となります。
また「コピーの画質が悪い」「必要な部分が切れている」といったケースも審査の遅延につながります。さらに「異なる名義の書類を混在させる」のも避けるべきです。たとえば、給与明細は契約名義人のもので統一し、他の人のものを混ぜないようにしましょう。
同棲解消や将来を見据えた契約の注意点も知っておこう(+よくある質問)

同棲カップルが賃貸契約を結ぶ際は、現在のことだけでなく将来的なリスクも考慮しておくことが重要です。
特に、関係が変化した場合の対応については、契約前にしっかりと話し合っておく必要があります。
契約者をどちらにするかで変わる将来リスク
契約名義人の選択は、将来的なトラブルを左右する重要な判断となります。
たとえば、関係が悪化して一方が退去することになった場合、契約名義人は引き続き家賃支払い義務を負うことになります。つまり、経済的により安定している方を契約名義人にしておく方が、リスク管理の観点からは適切だと言えるでしょう。
一方で、将来的に結婚を予定している場合は、どちらが契約名義人であっても大きな問題にはなりにくいものです。お二人の関係性や将来設計に応じて、慎重に判断することをおすすめします。
同棲解消時の違約金・再契約のポイント
万が一の同棲解消に備えて、契約内容もしっかりと確認しておきましょう。
まず注意すべきは「短期解約違約金」の有無です。契約から一定期間内(通常1〜2年)に解約する場合、違約金が発生する物件があります。また「原状回復費用の負担割合」についても、事前に話し合っておくことが大切です。
もし一方が退去して、もう一方が住み続ける場合は「契約者変更」の手続きが必要になります。この際、新たに審査が行われることもあるため、事前に管理会社に確認しておくと安心です。
よくある質問(FAQ:婚約者と記載するのは有利?/審査に落ちた時の次の一手は?)
最後に、同棲カップルからよく寄せられる質問についてお答えしていきます。
Q: 申込書に「婚約者」と記載した方が審査に有利になりますか?
A: 必ずしも有利とは言えません。むしろ虚偽記載のリスクを考えると、正直に「恋人」や「パートナー」と記載する方が安全です。
Q: 審査に落ちてしまった場合、次はどうすればいいでしょうか?
A: まずは不動産会社に落ちた理由を確認しましょう。その上で、家賃を下げる、保証人を追加する、契約名義人を変更するなどの対策を検討してみてください。
Q: 同棲カップル向けの物件を探すコツはありますか?
A: 「カップル歓迎」「二人入居可」といった条件で絞り込むことが効果的です。また、個人大家さんの物件は比較的柔軟な審査をしてくれることが多いので、積極的に検討してみることをおすすめします。
まとめ
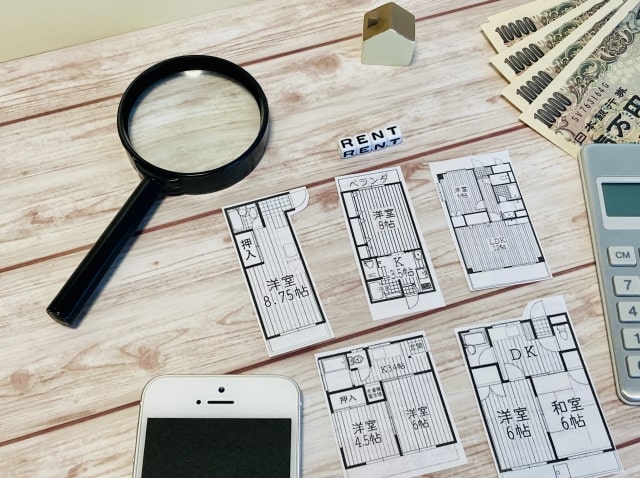
同棲カップルの入居審査は、確かに単身者と比べて複雑な面があります。しかし、適切な準備と対策を行えば、十分に審査を通過することが可能です。
重要なポイントを改めて整理すると、まず家賃は年収の36分の1以内に設定し、より収入が安定している方を契約名義人にすることが基本となります。また、必要書類は早めに準備し、不備がないよう入念にチェックしておきましょう。
年収や雇用形態に不安がある場合でも、諦める必要はありません。追加の証明書類を活用したり、保証人を立てたりすることで、審査通過の可能性を高めることができます。
新生活への第一歩として、お二人にとって最適な物件が見つかることを心から願っています。不安なことがあれば、遠慮なく不動産会社に相談し、納得のいく契約を結んでくださいね!