同棲の固定費はいくら必要?内訳・目安・分担ルールをわかりやすく解説

「同棲を始めたいけど、毎月いくらかかるんだろう…」
そんな不安を抱えているカップルも多いのではないでしょうか。
同棲は二人の新しい生活のスタート地点ですが、お金のことをきちんと把握していないと、後々トラブルの原因になってしまうことも。特に固定費は毎月確実にかかる支出なので、事前にしっかり理解しておくことが大切です。
この記事では、同棲カップルの固定費の内訳から平均額、分担ルール、節約のコツまで詳しくお伝えしていきます。二人で快適な同棲生活を送るための第一歩を踏み出しましょう!
同棲カップルの固定費、どんな項目がある?基本の内訳を整理

まずは同棲生活でかかる「固定費」の全体像を把握していきましょう。
そもそも固定費とは何か、どんな項目があるのかを知ることで、毎月の支出をコントロールしやすくなります。
固定費と変動費の違いとは?
生活費を管理する上で、まず理解しておきたいのが「固定費」と「変動費」の違いです。
固定費とは、毎月ほぼ一定の金額がかかる支出のこと。一方で変動費は、使い方次第で金額が変わる支出を指します。
具体的には、家賃や水道光熱費、通信費などが固定費に該当します。対して食費や交際費、娯楽費などは変動費です。固定費は一度見直せば継続的な節約効果が得られるため、家計管理において特に重要な項目といえるでしょう。
家賃・水道光熱費・通信費など主要項目
同棲カップルの固定費における主要な項目を見ていきましょう。
最も大きな割合を占めるのが「家賃」です。これは賃貸物件の月額賃料と管理費・共益費を合わせたもの。次に「水道光熱費」があり、電気代・ガス代・水道代の3つが含まれます。
「通信費」も見逃せない固定費です。スマートフォンの月額料金やインターネット回線の費用がこれにあたります。さらに「保険料」として、賃貸契約時に加入が必須の火災保険や、個人で加入している医療保険・生命保険なども固定費に分類されます。
意外と忘れがちな固定費(駐車場代・保険・サブスクなど)
主要な固定費以外にも、見落としがちな項目がいくつかあります。
「駐車場代」は車を所有しているカップルには必須の費用です。賃貸物件に駐車場が付いていない場合、月額1万円〜3万円程度かかることも。また「サブスクリプションサービス」も立派な固定費。動画配信サービスや音楽配信サービス、オンラインストレージなど、気づかないうちに複数契約していることもあるでしょう。
そのほか、奨学金の返済や習い事の月謝、ジムの会費なども固定費に含まれます。これらは個人差が大きいものの、積み重なると意外と大きな金額になるため、二人でしっかり確認し合うことが大切です!
家賃は手取りの何%が目安?固定費全体のバランスを考える

固定費の中でも最も大きな割合を占める家賃。
ここでは、無理のない家賃設定と、固定費全体のバランスについてお話ししていきます。
家賃は「手取り合計の25〜30%」が目安
一般的に、家賃は手取り収入の25〜30%以内に抑えるのが理想とされています。
ただし、これは一人暮らしの場合の目安。同棲の場合は二人の手取り合計額で計算していきましょう。たとえば二人の手取り合計が40万円なら、家賃は10万円〜12万円程度が適正範囲です。
注意したいのは、「手取り」で計算するという点。額面収入ではなく、税金や社会保険料を差し引いた実際に使える金額で考えることが大切です。手取り額は一般的に額面の約80%程度になるため、給与明細でしっかり確認しておきましょう。
家賃を基準にした固定費配分の考え方
家賃が決まったら、次は他の固定費とのバランスを考えていきます。
理想的な配分としては、手取り収入に対して住居費が25〜30%、水道光熱費が5%程度、通信費が3〜5%程度といわれています。たとえば手取り合計40万円の場合、家賃10万円、水道光熱費2万円、通信費1.5万円といった具合です。
ただし、これはあくまで目安。都心部に住む場合は家賃の割合が高くなりやすく、地方では車の維持費がかさむことも。二人のライフスタイルや価値観に合わせて、柔軟に調整していくことをおすすめします!
収入に合わせた無理のない家計設計のポイント
無理のない家計設計のポイントは、「先取り貯蓄」を確保することです。
収入から先に貯蓄分を差し引き、残ったお金で生活するのが基本。そのうえで固定費が変動費よりも多くならないように調整していきましょう。固定費が生活費の大半を占めてしまうと、急な出費に対応できなくなるからです。
また、二人の収入に差がある場合は、無理に折半にこだわらないことも大切。収入比に応じた負担割合にすることで、どちらか一方に負担が偏るのを防げます。お互いが納得できる形で固定費を分担し、余裕のある家計設計を目指してみてください!
2人暮らしで実際にかかる固定費の平均額【公的データ+実例】

ここからは、実際のデータをもとに二人暮らしの固定費を見ていきましょう。
公的な統計データと実例を合わせてご紹介します。
総務省統計から見る2人以上世帯の平均支出
総務省の「家計調査報告」によると、2023年の二人以上世帯における消費支出の平均は月額約29.4万円です。
このうち住居費(家賃など)は平均で約1.8万円となっていますが、これは持ち家世帯も含めた数字のため実態よりかなり低くなっています。賃貸暮らしの場合、東京23区の1LDK・2K・2DKの家賃相場は約11.9万円(2025年1月時点)。地域によって大きく異なりますが、都市部では家賃だけで10万円前後かかることを覚えておきましょう。
水道光熱費は平均で月2万円前後、通信費は平均で1.5万円程度が目安となります。これらを合わせると、二人暮らしの基本的な固定費は15万円〜17万円程度になることが分かります。
都市部と地方の違い(車の有無でどう変わる?)
固定費は住むエリアによって大きく変わってきます。
都市部では家賃が高い一方、公共交通機関が発達しているため車を持たないカップルも多いです。対して地方では家賃は安めですが、車が必須となるケースがほとんど。車を所有すると、駐車場代・ガソリン代・自動車保険・車検費用などで月3万円〜5万円程度の追加支出が発生します。
たとえば東京で家賃12万円・車なしの場合と、地方で家賃7万円・車ありの場合を比較すると、固定費の総額はそれほど変わらないことも。ただし、生活の質や利便性は大きく異なるため、二人のライフスタイルに合った選択をすることが大切です!
実際の同棲カップルの生活費シミュレーション例
では、具体的なシミュレーションを見ていきましょう。
【都市部・手取り合計40万円の場合】
- 家賃(管理費込み):11万円
- 水道光熱費:2万円
- 通信費(スマホ2台+ネット):1.5万円
- 保険料:1万円
- サブスク:0.5万円
- 固定費合計:16万円
【地方・手取り合計35万円の場合】
- 家賃(管理費込み):7万円
- 水道光熱費:1.8万円
- 通信費(スマホ2台+ネット):1.5万円
- 保険料:1万円
- 車関連費:4万円
- 駐車場代:1万円
- 固定費合計:16.3万円
このように、地域や生活スタイルによって内訳は変わりますが、固定費の総額はおおむね15万円〜18万円程度になるケースが多いです。自分たちの状況に当てはめて、シミュレーションしてみてください!
揉めない!同棲カップルの固定費分担ルール3パターン

固定費の分担方法は、カップルによってさまざま。
ここでは代表的な3つのパターンと、それぞれのメリット・デメリットをご紹介していきます。
完全折半のメリット・デメリット
最もシンプルなのが、すべての固定費を完全に折半する方法です。
メリットは、計算が簡単で公平感があること。どちらか一方が損をしている感覚になりにくく、お金のことで揉めにくいのが特徴です。また、お互いに責任感を持って家計管理ができるでしょう。
デメリットとしては、収入に差がある場合に不公平感が生まれやすいこと。一方が手取り30万円、もう一方が20万円という状況で完全折半にすると、収入の少ない側の負担が重くなってしまいます。また、急な収入変動があった場合に柔軟な対応がしにくいのも難点です。
収入比で分担する場合の公平性
収入に応じて負担割合を決める方法もあります。
たとえば手取り30万円と20万円のカップルなら、3:2の割合で固定費を分担するというもの。この方法のメリットは、収入差があっても公平感を保ちやすいこと。それぞれの収入に対する負担率が同じになるため、納得感が得られやすいです。
デメリットは、毎回の計算がやや複雑になること。また、収入が変動するたびに負担割合を見直す必要があるため、手間がかかります。さらに、お互いの収入を正確に把握し続ける必要があるため、プライバシーに対する考え方によっては抵抗を感じるかもしれません。
項目ごとに分ける方法と注意点
固定費の項目ごとに担当を決める方法もあります。
たとえば「家賃は片方が、水道光熱費と通信費はもう片方が負担する」といった具合です。この方法のメリットは、それぞれが明確な責任を持てること。支払い忘れのリスクも分散できます。
ただし注意点として、項目によって金額に大きな差が出る可能性があること。家賃だけで10万円、その他の固定費が合計5万円という場合、明らかに不公平になってしまいます。定期的に負担額を見直し、バランスを調整することが大切です!
名義・引き落とし口座・ポイント還元の工夫
固定費の分担を考える際、名義や支払い方法も重要なポイントです。
賃貸契約の名義は一人にするのが一般的ですが、その場合でも家賃は二人で分担できます。引き落とし口座は、共同口座を作って二人で管理する方法もありますし、どちらか一方の口座から引き落として後で精算する方法もあるでしょう。
ポイント還元の工夫も見逃せません。クレジットカード払いにすればポイントが貯まるため、固定費の支払いに活用するのがおすすめ。ポイント還元率の高いカードを選び、貯まったポイントは二人で使うルールにしておけば、実質的な節約にもなります!
まずどこを見直す?固定費を減らす優先順位チェックリスト
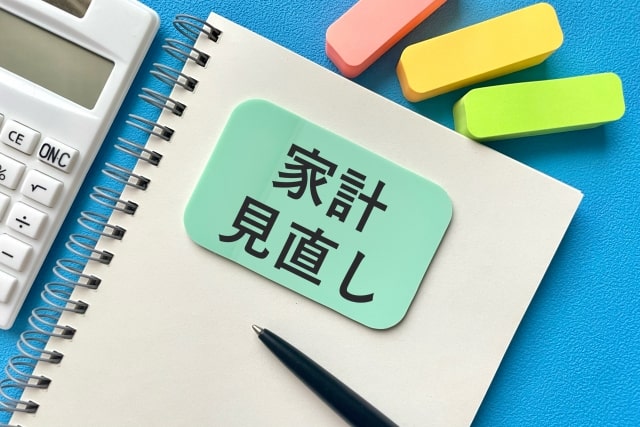
固定費を節約したいけど、何から手をつければいいか分からない…
そんな時は優先順位をつけて、効果の高いものから見直していきましょう。
通信費(回線・スマホプラン)を見直す
最も手軽に節約できるのが通信費です。
大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで、一人あたり月3,000円〜5,000円の節約になることも。たとえば楽天モバイルなら3GB未満で月1,078円、HISモバイルなら3GBで770円といった具合に、大手キャリアの5分の1以下の料金で利用できます。
二人とも格安SIMに変更すれば、合計で月6,000円〜1万円の節約が可能。年間にすると7万円〜12万円もの差になるため、真っ先に検討したい項目です。ただし、通信速度や電波の安定性も考慮して、自分たちに合ったサービスを選んでみてください!
電気・ガスの切り替えで節約
電力自由化・ガス自由化により、自由に電力会社・ガス会社を選べるようになりました。
現在契約している会社より安いプランがないか、定期的にチェックしてみましょう。電力比較サイトを使えば、住んでいる地域で利用できるお得なプランを簡単に見つけられます。電気とガスをセットで契約すると割引になるケースも多いです。
切り替えによって月1,000円〜2,000円程度の節約ができれば、年間で1.2万円〜2.4万円の削減に。手続きもオンラインで完結することがほとんどなので、手間をかけずに固定費を下げられます!
サブスクを棚卸しして取捨選択
意外と見落としがちなのがサブスクリプションサービスです。
動画配信、音楽配信、オンラインストレージ、雑誌読み放題…気づけば複数のサブスクに加入していることも。まずは現在契約しているサービスをすべてリストアップしてみましょう。そのうえで、本当に使っているものだけを残し、使用頻度の低いものは解約します。
二人で契約が重複しているサービスがあれば、一つにまとめるのも有効。たとえば動画配信サービスを一つの契約でシェアすれば、月1,000円程度の節約になります。小さな金額でも積み重なれば大きな差になるため、しっかり見直してみてください!
保険の重複をチェックして整理
保険も見直しポイントの一つです。
同棲を機に、お互いが加入している保険を確認してみましょう。二人とも同じような内容の医療保険に入っている場合、どちらか一方で十分なケースもあります。また、賃貸の火災保険も、不動産会社指定のものより安いプランが見つかることも。
ただし、保険の見直しは慎重に行うことが大切。必要な保障まで削ってしまっては本末転倒です。保険の専門家に相談しながら、本当に必要な保障を適切な金額で確保するよう心がけてみてください!
同棲生活を長く続けるために知っておきたい「初期費用と将来費用」

固定費だけでなく、同棲を始める前後にかかる費用も把握しておきましょう。
ここでは初期費用と、将来的に必要になる費用について詳しくお伝えしていきます。
入居時に必要な初期費用の相場
同棲を始める際、最も大きな出費となるのが賃貸物件の初期費用です。
一般的に、敷金・礼金・仲介手数料・前家賃・火災保険料などを合わせて、家賃の4〜6か月分が必要といわれています。たとえば家賃10万円の物件なら、40万円〜60万円程度。これに引っ越し費用が二人分で6万円〜10万円程度、家具・家電の購入費が20万円〜30万円程度かかります。
すべて合わせると、同棲の初期費用は家賃の7〜8か月分、金額にして70万円〜100万円程度が相場。かなり大きな出費になるため、計画的に貯金しておくことが大切です!
同棲1か月目にかかる思わぬ出費
初期費用を払い終えても、1か月目はまだ油断できません。
入居後に必要なものが見つかり、追加で購入することも多いです。たとえばカーテンやカーペット、収納用品、調理器具など、細かいものを買い足していくと5万円〜10万円程度かかることも。また、引っ越し直後は外食が増えがちなので、食費も通常より高くなります。
さらに、初月は家賃以外に日割り家賃が発生することもあるため、想定より支出が多くなりやすいです。初期費用とは別に、予備費として10万円程度用意しておくと安心でしょう!
更新料や引越し費用など将来のコスト
同棲生活が軌道に乗った後も、定期的にかかる費用があります。
賃貸契約は通常2年更新のため、更新時に更新料(家賃1か月分程度)や火災保険の更新料が必要に。家賃10万円なら、2年に1度12万円〜15万円程度の出費が発生します。月割りにすると5,000円〜6,000円程度ですが、まとまった金額が必要になるため計画的に貯めておきましょう。
また、同棲を解消したり結婚を機に新居に引っ越したりする際も、再び初期費用と引っ越し費用がかかります。将来的な出費も見据えて、毎月の貯金額を設定しておくことをおすすめします!
結婚を視野に入れた費用設計の考え方
結婚を前提とした同棲なら、将来の費用設計も大切です。
結婚式や新婚旅行、新居の購入など、大きな出費が控えています。結婚式は平均で300万円〜400万円程度、住宅購入の頭金は物件価格の1〜2割が目安。これらの費用を見据えて、同棲中から計画的に貯金していく必要があります。
たとえば3年後の結婚を目指すなら、月10万円ずつ貯金すれば360万円貯まる計算です。固定費を抑えることで、将来のための貯金もしやすくなるため、長期的な視点で家計を管理していくことが大切です!
まとめ

同棲カップルの固定費は、家賃・水道光熱費・通信費を中心に月15万円〜18万円程度が相場です。
家賃は二人の手取り合計の25〜30%以内に抑え、その他の固定費とのバランスを考えることが大切。分担方法は完全折半・収入比・項目別など、二人に合った形を選びましょう。
固定費を見直す際は、通信費・光熱費・サブスク・保険の順に優先して取り組むのがおすすめです。
同棲は二人の生活を共にする大切な時間。お金のことでギクシャクしないよう、事前にしっかり話し合い、お互いが納得できるルールを作っておくことが、長続きする同棲の秘訣です。この記事を参考に、素敵な同棲生活をスタートさせてみてください!