同棲の光熱費は平均いくら?二人暮らしの相場と節約・管理のコツを徹底解説

「同棲を始めたら光熱費ってどれくらいかかるんだろう…」
「一人暮らしよりもどのくらい高くなるの?」
同棲を考えているカップルにとって、毎月の光熱費は重要な関心事です。光熱費は住んでいる地域や季節、ライフスタイルによって大きく変動していきます。
この記事では、同棲カップルの光熱費の平均相場から、揉めない割り勘ルール、今すぐできる節約術まで詳しくお話ししていきます。二人の新生活を快適に始めるための参考にしてみてください!
二人暮らしの光熱費は平均いくら?最新データで徹底解説

まずは、実際の数字を確認していきましょう。二人暮らしの光熱費は1ヶ月あたり21,619円が平均となっていますが、内訳を詳しく見ていくことで、より具体的な家計計画を立てることができます。
電気代の平均と割合
二人暮らしの1ヶ月あたりの電気代の平均は10,940円です。この金額は光熱費全体の約5割を占めており、最も大きな比重を持っています。
電気代が高い理由として、一人暮らしから二人暮らしになることで部屋が広くなりがちなことがあります。そのため、冷暖房にかかる消費電力も増加する傾向にあります。
また、電気代は季節によっても変わり、冷暖房を使用する夏や冬は特に高くなりやすいです。特に冬場は電気代が高くなる傾向があるため、季節変動も考慮しておくことが大切です。
ガス代の平均と地域差(都市ガス/プロパン)
二人暮らしのガス代の平均は1ヶ月あたり4,971円となっています。ただし、注意していただきたいのは都市ガスとプロパンガスでは料金に大きな差があることです。
都市ガスの2人暮らしの平均ガス代は月4,000円~7,000円程度なのに対し、プロパンガスの平均ガス代は月6,000円~10,000円程度です。つまり、プロパンガスは都市ガスよりも1.5〜2倍高い計算になります。
これは、プロパンガスの従量単価の全国平均は約700円ですが、都市ガスの平均単価が約400円という単価の違いと、プロパンガスの基本料金が1,650円~2,310円(税込)となっていることが多く、基本料金だけでプロパンガスの方が1,000円以上高くなることもあるためです。
水道代の平均と算出方法(二か月検針の月額換算)
2人暮らしだと4,248円/月が水道代の平均額となっています。水道料金は地域によって差があり、一番料金が安いのは四国地方で4,082円、一番高い東北地方の6,299円と比べると、月に約2,200円もの差があります。
水道代の計算で注意したいのは、検針が2カ月ごとに行われることです。そのため、請求書に記載される金額を2で割ることで、月額の目安を把握することができます。
光熱費合計と年間に換算した目安
これらをまとめると、二人暮らしの光熱費は月平均約2.1万円となり、年間では約25万円前後になります。家賃以外の費用はおよそ7万〜12万円程度となりますので、光熱費は生活費の重要な要素といえるでしょう。
家計全体に占める割合としては、理想的には月収の7〜10%程度に抑えられると良いとされています。
季節や地域でどれだけ変わる?光熱費の上下幅を把握しよう
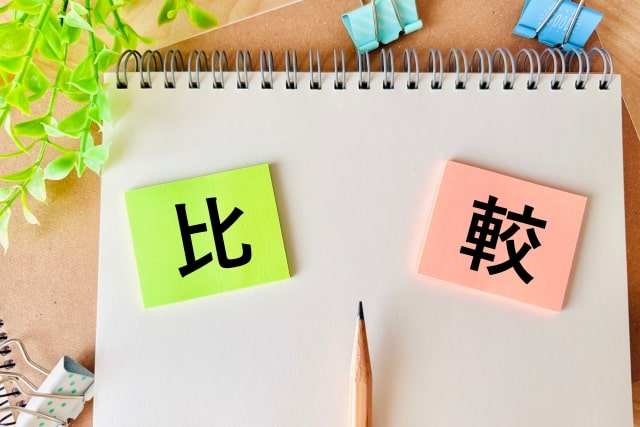
光熱費は季節や地域によって大きく変動していきます。この変動を理解することで、より正確な家計計画を立てることができます。
夏と冬のピーク時にかかる費用
2月は、暖房の需要が高くなる地域が多いため、光熱費が最も高騰する月です。夏と冬を比較すると冬のほうが光熱費は高く、2月と8月の電気代で比較すると約1.8倍程度の違いがあります。
冬場の暖房費用は特に注意が必要で、寒冷地では平均の1.3〜1.5倍になることも珍しくありません。また、一般的に冷房よりも暖房の方が電気使用量が多いため、夏よりも冬の方が電気代が高くなる傾向にあります。
寒冷地と温暖地での違い
地域による差も非常に大きな要素です。光熱費が一番高い北海道(25,089円)と電気代が一番安い九州地方(16,841円)では、1ヶ月あたりの光熱費が8,248円も異なる結果です。
光熱費全体の平均額を見ると、北海道や東北、北陸など冬の寒さが厳しい地域では全国平均よりも金額が高くなっているのがわかります。一方で、沖縄などの温暖な地域では比較的低く抑えられる傾向があります。
オール電化物件の特徴と注意点
オール電化物件にお住まいの場合、ガス代は不要になりますが、その分電気代が高くなります。関西電力の調査結果によると、2020~2021年におけるオール電化の二人世帯の平均月額電気代は13,406円です。
この結果を見るとオール電化のほうが光熱費を抑えやすいことがわかりますが、深夜電力プランを活用することでさらに節約効果を期待することができます。
在宅時間や生活習慣でここまで違う!ライフスタイル別の目安
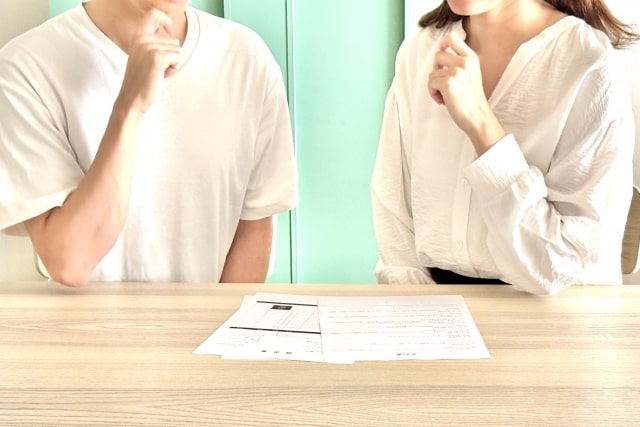
同じ二人暮らしでも、ライフスタイルによって光熱費は大きく変動していきます。自分たちの生活パターンと照らし合わせて確認してみてください。
在宅ワークが多い場合の光熱費
在宅勤務が増えている昨今、家にいる時間が長いほど光熱費は上昇していきます。二人のうち一人が在宅勤務であったり、ペットのために終日室温管理をしていたりすると、三人暮らしや四人暮らしの電気代と並ぶ家もたくさんあるよという実情があります。
具体的には、エアコンの稼働時間延長、パソコンやモニターなどの電子機器使用、照明の点灯時間増加などにより、月2,000〜5,000円の上乗せになるケースが多く見られます。
共働きで日中不在の場合
逆に、共働きで日中家を空けることが多いカップルの場合、平均よりも光熱費を抑えやすい傾向にあります。冷暖房や照明を使わない時間が長いため、基本料金中心の支払いに近くなっていきます。
ただし、帰宅時間が遅くなることで、深夜の電力使用量が増える場合もあるため、電力プランの見直しを検討することをおすすめします。
お風呂の入り方(湯船派・シャワー派)による差
入浴習慣は光熱費に大きな影響を与えます。毎日湯船にお湯を張る場合、ガス代と水道代で月3,000円以上の増加も珍しくありません。一方、シャワー中心の生活では使用量を大幅に抑えることができます。
例えば、200リットルの浴槽のお湯を2時間放置して、温度が4.5℃下がったお湯を温めなおすのに必要なガス代は、年間で約年間6,190円という試算もあります。
料理や家電使用頻度が高い家庭
自炊派のカップルの場合、ガスコンロの使用頻度が高くなるため、ガス代の増加に加えて水道代も上昇していきます。また、食洗機や電子レンジ、炊飯器などの調理家電を頻繁に使用する場合は、電気代への影響も考慮しておきましょう。
一方で、外食中心の生活では光熱費は抑えられますが、食費との兼ね合いで総合的に判断することが重要です。
同棲で揉めないための光熱費の割り勘ルールと管理方法

お金の問題は同棲生活で最もトラブルになりやすい要素です。事前にルールを決めておくことで、円満な関係を維持していきましょう。
等分にする場合のメリット・デメリット
最もシンプルな方法が、光熱費を等分に分けることです。計算が簡単で分かりやすく、お互いに公平感を感じやすいのがメリットです。
ただし、収入に大きな差がある場合や、在宅時間に偏りがある場合には不公平感が生まれやすいというデメリットがあります。また、節約への意識の差も問題になることがあります。
収入割合に応じた負担方法
収入の差がある場合の家賃の分担方法として、収入比率に応じて光熱費を分担する方法もあります。例えば、収入が6:4の比率であれば、光熱費も同じ比率で負担していきます。
この方法では双方が納得しやすい一方で、収入の変動があった場合の調整や、毎月の計算がやや複雑になるという面もあります。
共同口座やアプリを使った管理の工夫
共同出資の方法として、光熱費専用の共同口座を作る方法があります。それぞれが決まった金額を入金し、そこから光熱費を支払うことで透明性を確保できます。
また、家計簿アプリを活用して支出を可視化することで、お互いが使用状況を把握しやすくなり、節約への意識も高まっていきます。
すぐできる節約術と固定費見直しのステップ

具体的な節約方法をご紹介していきます。小さな工夫の積み重ねが、年間で大きな節約効果を生み出します。
電気代を抑えるコツ(エアコン・照明・家電)
エアコンの節約では、エアコンの電気代がもっともかからない運転方法は、自動運転です。自動運転モードにして、サーキュレーターや扇風機を上向きに回して空気を循環させると、エアコンの電気代を節約できます。
照明についてはLED電球への切り替えが効果的で、白熱電球と比較して約80%の電力削減が可能です。また、待機電力対策として、使わない家電のコンセントを抜く習慣も重要です。
ガス代を節約する工夫(給湯・調理・お風呂)
ガス代節約の要となるのは給湯温度の調整です。設定温度を1℃下げるだけで約10%の節約効果が期待できます。
調理面では、電子レンジを活用した下茹でや、圧力鍋を使った時短調理などが効果的です。また、二人の入浴時間を空けないことで追い焚きの回数を減らすことも重要なポイントです。
水道代の節約ポイント(洗濯・食器洗い・お風呂)
洗濯では、まとめ洗いを心がけることで水道代と電気代の両方を節約できます。食器洗いでは、油汚れを拭き取ってから洗うことで使用水量を削減できます。
節水シャワーヘッドの導入も効果的で、節水シャワーヘッドに替えるだけで水道代を抑えることが可能です。水圧が強いタイプを選ぶことで、節水しながらも快適性を保つことができます。
電力・ガス会社のプラン見直し手順
東京電力エナジーパートナーの一般家庭向けプラン「従量電灯B」で10A(アンペア)下げた場合、1年で3,741円、5年間では18,705円節約できます。契約アンペア数の見直しから始めて、ライフスタイルに合ったプランへの変更を検討してみてください。
ガス会社についても、今より安いガス料金を提供しているガス会社に変更できれば、それだけでガス代を抑えられる可能性もあるので、複数社での比較検討をおすすめします。
知っておきたい!同棲生活でかかるその他の固定費とのバランス

光熱費だけでなく、生活費全体のバランスを考えることが重要です。
家賃と光熱費のバランス
家賃を含めた生活費の合計は「20万円前後」が多くのカップルの現実的なラインとされています。理想的には、家賃と光熱費の合計を手取り収入の50%以内に収めることが推奨されています。
食費・通信費との比較
食費:約30,000〜50,000円(自炊中心か外食中心かで差あり)、通信費(Wi-Fi、スマホ):約10,000〜15,000円が相場となっています。光熱費約2.1万円と合わせて考えると、これらの固定費だけで6〜8万円程度になります。
生活費全体での適正割合
理想的な家計割合としては、住居費(家賃+光熱費)25〜30%、食費20〜25%、光熱費7〜10%、貯金15〜20%というバランスが推奨されています。
緊急時や将来に備えて、少しずつ貯金するように意識しましょうということも忘れずに、計画的な家計管理を心がけていきましょう。
まとめ

同棲の光熱費について詳しくお話ししてきました。二人暮らしの光熱費は月平均約2.1万円が相場ですが、地域や季節、ライフスタイルによって大きく変動することがお分かりいただけたかと思います。
特に重要なのは、事前にお金のルールを決めておくことと、小さな節約の積み重ねを続けることです。電力・ガス会社の見直しや契約プランの変更など、根本的な固定費削減も検討してみてください。
同棲生活を始めるカップルの皆さんには、お互いの価値観を尊重しながら、無理のない範囲で節約に取り組んでいただくことをおすすめします。光熱費を上手に管理して、素敵な二人の時間を過ごしてくださいね!