同棲するとき契約者はどっち?単独・連名の違いや名義変更まで徹底解説

「彼氏と同棲したいけど、契約者はどっちにすればいいの?」
そんな疑問を抱えながら賃貸物件を探している方も多いのではないでしょうか。
同棲は新しい生活の始まりですが、賃貸契約では一人暮らしとは異なる注意点があり、どちらが契約者になるかで審査の通りやすさや将来的な手続きも変わってきます。
この記事では同棲時の契約者の選び方から単独名義と連名契約の違い、そして将来の名義変更まで詳しくお伝えしていきます。安心して同棲生活をスタートさせるためのポイントをマスターしていきましょう!
同棲の契約者はどちらにするべき?基本の考え方

同棲を始める際、まず決めなければならないのが契約者を誰にするかという問題です。実は、契約者はどちらでも問題ありませんが、いくつかのポイントを考慮して決めることが大切になります。
収入・勤続年数・信用情報から判断するポイント
同棲時の契約者選びで最も重要なのは、安定した収入があることです。
一般的に、年収が高い、または収入が安定しているほうを契約者にすれば、入居審査は通りやすいといえます。これは、入居審査では家賃の支払い能力が最重視されるためです。
具体的には以下のような基準で判断すると良いでしょう。まず月収と家賃のバランスを確認し、一般的には家賃が月収の3分の1以内に収まることが理想的とされています。次に勤続年数もチェックポイントで、長期間同じ職場で働いている人の方が安定性があると判断されがちです。
さらに雇用形態も影響し、正社員の方が契約社員やアルバイトよりも有利になることが多いでしょう。信用情報についても重要で、過去にクレジットカードの延滞やローンの滞納がある場合は審査に影響する可能性があります。
家賃補助や会社規程を考慮すべきケース
勤務先からの家賃補助を受けられるかどうかも、契約者選びの重要な判断材料です。
現在は夫名義で契約しているが、妻が勤務している会社の家賃補助を受けたいので妻名義に変更したいというケースは珍しくありません。家賃補助は契約者本人にのみ支給されることが一般的なため、補助を受けられる側を契約者にすることで家計の負担を軽減できます。
ただし、会社の規程によっては結婚していることが条件となる場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
「どちらでも可能」の前提を押さえる
同棲するときの契約名義は、彼氏・彼女のどちらでも問題ありません。契約名義が彼女であっても、入居審査で不利になることもないでしょう。
つまり、性別による差別はなく、純粋に支払い能力や安定性で判断されるということです。ただし、実際のところ同棲を開始する場合は「男性側」を主契約者にすることが多いですという傾向はあるものの、これは単なる慣習であり、必須ではありません。
単独名義と連名契約の違いとメリット・デメリット
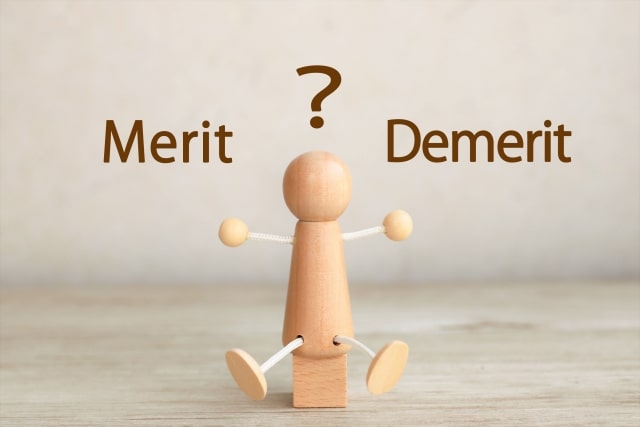
同棲する際の賃貸契約方法は、大きく分けて単独名義と連名契約の2つがあります。それぞれに特徴があるため、しっかりと理解して選択することが重要です。
単独名義のメリット・デメリット
単独名義とは、カップルのうち1人だけが契約者となる方法です。
まずメリットから見ていくと、手続きが簡単であることが最大の利点でしょう。契約者が一人の場合、入居審査時「家賃支払い能力がある」と判断しているため、同棲が解消となり、同居人が退去したとしても、管理会社などは「滞納リスクは少ない」と判断するため、連名契約より入居審査が通りやすくなります。
一方でデメリットとしては、契約者でない同居人は各種手続きに関わることができません。また、家賃補助を両者が受けたい場合でも、契約者分しか受けられないという制約があります。
連名契約のメリット・デメリット
連名契約(共同名義)は、2人以上で一緒に賃貸借契約を結ぶ方法です。契約をした全員が契約者となります。
メリットとしては、まず両者とも契約の権利を持つため、各種手続きに平等に関わることができます。さらに複数人での契約は家賃滞納リスクが低いため、入居審査に通りやすくなりますという点も魅力的でしょう。加えて、両者とも家賃補助を受けられる可能性があります。
しかしデメリットも存在し、契約者の人数が増えると、家賃の請求が複雑になり滞納リスクが高まりますため、大家さんが敬遠することがあります。また連名での契約は契約者が複数人になりますから、何かの連絡がある場合や家賃の請求などをする場合にも煩雑になりがちです。
どちらを選ぶべきか判断するチェックリスト
以下のポイントを確認して、どちらの契約方法が適しているか判断してみてください。
まず物件が連名契約を認めているかを確認しましょう。連名契約を認めていない仲介(管理)会社が多いのが現実となっていますため、事前の確認が必須です。
次に収入状況をチェックし、片方の収入だけで審査に通る見込みがあるなら単独名義でも問題ないでしょう。しかし両方の収入を合算しないと審査が心配な場合は、連名契約を検討してみてください。
また家賃補助の有無も重要で、両者とも受けたい場合は連名契約が有利になります。最後に将来の予定も考慮し、結婚予定があるなら単独名義でも十分ですが、まだ未定なら連名契約の方が安心かもしれません。
保証人・保証会社はどうなる?契約形態別の必要条件

同棲時の賃貸契約では、保証人や保証会社の設定についても通常の契約とは異なる点があります。契約形態によって必要な手続きが変わってくるため、事前に理解しておくことが大切です。
単独名義の場合の保証人・保証会社の扱い
単独名義の場合、基本的には契約者1人分の保証人または保証会社の利用で足ります。
収入の多い方が契約者となった場合、契約した人にだけ連帯保証人をつけるのが一般的です。連帯保証人は通常、支払い能力がある、3親等以内の親族であることが基本で、契約者の両親や兄弟姉妹にお願いするのが一般的でしょう。
保証会社を利用する場合は、初年度の保証料は家賃の0.5~1カ月分が一般的で、毎年更新料がかかる場合もあります。費用は契約者が負担することになるため、事前に予算に組み込んでおくことが重要です。
連名契約の場合の保証人・保証会社の扱い
連名契約では、契約者それぞれに保証人が必要になることが一般的です。
それぞれが契約者となった場合には、それぞれに連帯保証人をつけることになります。つまり、契約者2人に対して連帯保証人も2人立てるのが基本となります。これは、契約者ごとに連帯保証人が必要ですという原則があるためです。
保証会社を利用する場合も同様で、各契約者が審査を受ける必要があります。ただし、契約者が二人の場合、2つの契約があるので保証料も倍額掛かりそうですが、最近は連名契約に対応している保証会社もあり、1契約分の保証料で済ますというケースも増えてきました。
保証会社利用時に注意すべきポイント
保証会社を利用する際には、いくつかの注意点があります。
まず、保証会社は基本的に不動産会社の関連会社や提携会社が指定した賃貸保証会社と契約することとなりますため、自由に選ぶことはできません。また、賃料を滞納した場合、保証会社が一時的に支払うものの、その費用は後日利用者に督促されますという点も理解しておく必要があります。
審査については、収入や職業、過去の信用情報が厳しくチェックされます。特に家賃と収入のバランス、過去の支払い遅延履歴が審査の重要な要素です。そのため、過去にクレジットカードの支払い遅延などがある場合は、審査に影響する可能性があることを覚えておきましょう。
契約申し込みに必要な書類と続柄の書き方
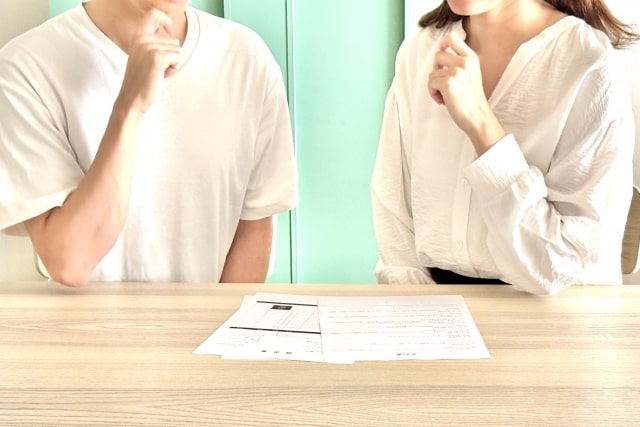
同棲時の賃貸契約では、単独名義と連名契約のどちらを選ぶかによって必要な書類の量が変わります。特に続柄の書き方については、適切に記載することが重要です。
必須書類チェックリスト(身分証・収入証明・住民票など)
同棲の賃貸契約で必要な基本書類をご紹介していきます。
まず身分証明書ですが、2人暮らしの契約の場合、契約者は2人となるため2人分の身分証明書の写しが必要になるのです。運転免許証やマイナンバーカードなど、写真付きの身分証明書のコピーを用意しましょう。
住民票についても2人分必要なのですが、このタイミングではお互いの住所が違っていても問題はありません。発行から3ヶ月以内の原本が必要で、続柄が記載されたものが必要ですため、窓口で続柄の記載を忘れずに依頼してください。
さらに収入証明書として給与明細書(直近3ヶ月分)や源泉徴収票、住民税決定通知書なども準備しておきましょう。
申込書の「続柄」はどう書く?(婚約者・同居人)
続柄の記載については、カップルの関係性によって書き方が変わります。
結婚する前提ならば「婚約者」、結婚前提でないのであれば「友人(同棲)」や「知人(同棲)」と書きましょう。ただし、現時点では結婚を考えていないカップルであっても、婚約者と書くことをすすめることがあります。その理由は、同居人と書くよりも婚約者と書いた方が大家さんからの信用を得やすいからです。
なお、同棲を考えたとき、続柄として考えられるのは「同居人」と「婚約者」の2つですが、どちらを選ぶかは将来の結婚予定や大家さんへの印象を考慮して決めると良いでしょう。
契約までの流れと期間(1〜2週間の目安)
同棲時の賃貸契約の流れは、一般的な契約と基本的には同じです。
一般的に、入居の申込から入居開始までの期間は2週間から1ヵ月程度です。ただし、同棲であれば、ひとりで住むのと違い、契約者をどちらにするかを事前に決めておく必要がありますため、事前準備が重要になります。
具体的な流れとしては、まず物件の申し込みを行い、必要書類を提出して審査を受けます。審査が通過したら重要事項説明を受け、賃貸借契約書を締結します。最後に初期費用を支払って鍵の受け渡しとなり、入居開始です。
スムーズな契約のためにも、遅くとも入居の申し込み時までには決めておきましょうというアドバイス通り、契約者や必要書類の準備は早めに進めておくことをおすすめします。
同棲解消・結婚時に名義をどうする?名義変更と再契約の注意点

同棲生活では、将来的に関係性が変わる可能性があります。同棲解消や結婚といった状況変化に備えて、名義変更や再契約の注意点を理解しておくことが大切です。
同棲解消時に必要な手続きと注意点
同棲を解消する際の手続きは、契約形態によって大きく異なります。
単独名義の場合、契約者本人が住み続けるのであれば全く問題ありません。同居人が退去するだけなら、管理会社への連絡と同居人変更の手続きを行うだけで済むでしょう。
しかし、契約者本人は契約物件から引っ越したが「住み続けているのは同居人」となるケースもあります。この場合は契約者でない人が住み続けることになるため、名義変更ではなく再契約が必要になります。
連名契約の場合はより複雑で、1人だけの契約解除ができないことですという大きな問題があります。共同名義の解除ができるのは、賃貸契約そのものを解約したときだけです。途中で一方だけが解約したくても、できない点に注意しましょう。
入籍・改姓時の名義修正と手続き方法
結婚によって氏名が変わる場合の手続きについてもご紹介していきます。
結婚などで苗字が変わった場合は名義変更が必要です。この場合は単純な名義変更手続きで対応できることが多く、手続きの際には氏名が変わったことが分かる身分証明書のコピーを求められることが多いようです。
契約者を妻のままにしておくのであれば再契約が必要になることはありません。姓が変わったことと同居人が増えただけで、契約上の名義人は同一のままとみなされるからです。つまり、契約者自身が結婚で苗字が変わった場合は、名義変更だけで済むということです。
ただし、名義変更の手続きを怠った場合、家賃の引き落としが出来なかったり、契約更新などに関わる書類が届かなかったりする可能性もありますため、速やかに手続きを行うことが重要でしょう。
名義変更ができない場合の再契約の流れ
名義変更では対応できず、再契約が必要になるケースもあります。
単純に契約上の名義人を変更するだけでスムーズに済ませられることもあれば、承諾するとしても再契約扱いになり、原状回復および敷金礼金が発生してしまうかもしれません。
再契約が必要な場合の流れとしては、まず現在の契約者が解約手続きを行います。同時に新しい契約者が新規申し込みを行い、改めて入居審査を受けることになるでしょう。審査通過後、新たな賃貸借契約を締結し、初期費用を支払います。
再契約や新規契約になる場合、敷金は前の名義人に返され、新たに敷金を納める必要がありますため、費用面での負担も考慮しておく必要があります。名義変更の手数料に決まりはなく、1万円から家賃1ヶ月分となることが多いようですが、再契約の場合はより多くの費用がかかることを覚えておきましょう。
よくある質問Q&A(家賃補助・名義変更・解約時の責任など)

同棲時の賃貸契約について、よくある疑問にお答えしていきます。
Q:家賃補助は両方とも受けられますか?
A:単独名義の場合、基本的には契約者分のみ受けられます。両方とも受けたい場合は連名契約を検討しましょう。ただし、会社によっては結婚していることが条件の場合もあるため、事前に人事部などに確認することをおすすめします。
Q:同棲中に一人が転勤になった場合はどうすれば良いですか?
A:単独名義で契約者が転勤する場合、同居人への名義変更または解約が必要です。連名契約の場合は一人だけの契約解除ができないため、一度全体の契約を解約して、残る人が再契約することになります。
Q:結婚前に同棲していた物件で、結婚後も住み続けることはできますか?
A:可能です。結婚による氏名変更があれば名義変更手続きを行い、夫婦として住み続けることができます。ただし、単身用物件の場合は2人入居を認めていない可能性があるため、事前に確認が必要でしょう。
Q:同棲解消時の責任はどうなりますか?
A:単独名義の場合、契約者が全責任を負います。連名契約では、解約まで両者とも責任を負い続けることになるため注意が必要です。
Q:入居審査で同棲だと不利になりますか?
A:法律上、婚姻関係にある夫婦に比べて、同棲カップルは審査に通りにくいといわれています。カップルは法的に見ると関係性が薄く、夫婦よりも別れる可能性が高いからです。しかし、結婚を前提にした同棲であれば、その旨を伝えたほうが良いでしょう。
Q:保証人を頼める親族がいない場合はどうすれば良いですか?
A:保証会社を利用することで解決できます。連帯保証人を頼める相手がいなくても、保証会社のみで契約できる物件であれば、連帯保証人が立てられなくても賃貸契約を結べるのが、保証会社を利用するメリットです。
まとめ

同棲時の賃貸契約では、契約者をどちらにするかから始まり、単独名義と連名契約の選択、必要書類の準備、そして将来的な名義変更まで、様々なポイントを考慮する必要があります。
最も重要なのは、収入の安定性や審査の通りやすさを基準に契約者を決めることです。また、将来の結婚や同棲解消の可能性も見据えて、最適な契約形態を選択することが大切になります。
同棲生活を安心してスタートさせるために、事前にパートナーとしっかりと話し合い、必要な手続きを漏れなく進めていくことをおすすめします。分からないことがあれば、遠慮なく不動産会社に相談して、理想の同棲生活を実現してください!