同棲の最低費用はいくら?50万円台から始められる節約術と相場を徹底解説

「同棲を始めたいけど、最低でもいくら必要なんだろう……」
恋人と一緒に暮らしたい気持ちがあっても、金銭面の不安で踏み切れない方は多いのではないでしょうか。同棲には初期費用や毎月の生活費がかかり、具体的な金額が見えないと計画を立てるのも難しいもの。
この記事では同棲に必要な最低費用から相場、節約術まで詳しくお伝えしていきます。工夫次第で50万円台からでも同棲をスタートできる方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください!
同棲に必要な最低費用はいくら?相場と”条件別シナリオ”を解説

同棲に必要な最低費用について、まず結論をお伝えしていきます。
新居を借りる場合の標準的な相場は家賃の7~8か月分、一般的に100万円程度が目安とされています。しかし、工夫次第でこの金額を大幅に抑えることも可能。
新居を借りる場合の標準相場(100万円前後が目安)
家賃10万円の物件を例にすると、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用だけで家賃の4~6か月分かかり、さらに引っ越し費用や家具家電購入費を加えると合計で家賃8~10か月分程度になります。
つまり家賃10万円なら80~100万円の費用が必要という計算に。これには賃貸契約費用、引越し代、家具家電代が含まれています。
工夫次第で最低50~60万円台でも可能なケース
ところが、条件を工夫すれば50万円台からでも同棲をスタートできます。
敷金礼金がゼロの物件を選ぶことで初期費用は大幅に安く抑えられるほか、フリーレント物件(入居後1~3か月程度の家賃が無料)を狙うのも効果的。さらに中古家電の活用やお互いの持ち物を持ち寄ることで、家具家電代を10万円以下に抑えることも可能です。
既存宅から同棲を始める場合のほぼゼロ円スタート
どちらか一方が一人暮らしをしている場合、もともと住んでいる部屋で同棲を始めれば、すでに家具や家電など必要なものが揃っていることが多く、敷金や礼金も不要で費用は必要最小限で済むというメリットがあります。
ただし、契約内容によっては同棲が契約違反となる場合があるため、事前の確認が必須。この場合なら実質的に引越し費用と追加の家具代程度で済むため、10万円以下でのスタートも十分可能でしょう。
初期費用の内訳と削れるポイント|必須項目と交渉で減らせる費用

初期費用を抑えるには、何にお金がかかるのかを詳しく知っておくことが重要です。それぞれの項目について、削減のコツもお伝えしていきます。
敷金・礼金の有無で大きく変わる
敷金とは、貸主側に預ける担保の意味合いを持つ預け金のようなもので、家賃の未払いや原状回復費用が発生していなければ、退去時に全額返金されることもあります。一方で、礼金は貸主側に対して謝礼の意味合いで支払う費用で、退去時などに返金されることがないのが特徴になります。
一般的には敷金・礼金ともに家賃1か月分ずつが相場ですが、物件によっては2~3か月分に設定されていることも。「ゼロゼロ物件」と呼ばれる、敷金や礼金を0円に設定している物件を選べば、20万円近い節約効果が期待できます。
仲介手数料・保証会社料の相場と削減のコツ
仲介手数料は法律上、家賃1か月分が上限とされており、不動産会社によって異なり、仲介手数料が半月~1か月分かかりますが、不動産会社によって異なります。半額キャンペーンを実施している会社を選べば、5万円程度の節約につながるでしょう。
保証会社料は家賃1か月分程度が相場ですが、会社によって料金設定が異なるため比較検討が大切。
前家賃・火災保険・鍵交換など”忘れがちな出費”
前家賃:入居時に翌月分の家賃を前払いするのが一般的で、これに加えて日割り家賃も発生します。さらに火災保険料(2万円程度)、鍵交換代(1~2万円)なども必要になるため、これらの費用も事前に見積もりに含めておきましょう。
交渉や物件選びで削れる費用(◎/○/△)の目安
各費用の削減可能性を整理すると次のようになります:
- 礼金・仲介手数料:交渉次第で削減可能(◎)
- 保証会社料:やや交渉可能(○)
- 敷金:原状回復費用なので削りにくい(△)
- 前家賃・火災保険:必須費用のため削りにくい(△)
効果的なのは最初から礼金なし物件を狙うことと、仲介手数料の安い不動産会社を選ぶことでしょう。
引越し費用と家具家電の”最低セット”|節約する具体的な方法

同棲の初期費用の中でも、引越し費用と家具家電代は工夫次第で大幅に削減できる項目です。具体的な節約方法をご紹介していきます。
引越し費用の相場と安くするタイミング
通常期の単身者(一人暮らし)で平均5万~6万円、繁忙期で平均6万~8万円、同棲を始める場合は二人分になるためさらに高くなります。つまり通常期なら10~12万円、繁忙期(2~4月)なら15万円以上かかることも。
時期をずらすだけで大幅な節約効果が期待できます。また、複数の引越し業者から見積もりを取ることで、3~5万円程度安くなるケースも珍しくありません。
さらに節約したい場合は、自分たちの車やレンタカーで引越し作業をすることで、ガソリン代やレンタカー代のみで引越しすることも可能です。
最低限そろえる家具家電リストと費用目安
同棲に必要な家具や家電をすべて揃えるとなると、20万円以上かかるのが一般的。最低限必要なアイテムと価格目安は以下の通りです:
- 冷蔵庫(2ドア):4~6万円
- 洗濯機:3~5万円
- 電子レンジ:1~2万円
- ベッド(ダブル):3~5万円
- カーテン:1~2万円
- 照明器具:1万円程度
- 炊飯器:1~2万円
これらの基本セットで15~25万円程度になります。
中古・レンタル・譲受を活用した節約テクニック
二人で持っているものをリストアップし、重複しているアイテムを洗い出すことから始めましょう。特に冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの大型家電は二人分あっても使いきれません。
また、親戚や友人から使わなくなった家具や家電を譲り受けたり、リサイクルショップで安く購入したりすることでも、費用を節約できます。
家電レンタルサービスを活用すれば、初期費用を月額料金に分散させることも可能。特に高額な冷蔵庫や洗濯機は、レンタルから始めて後から購入を検討するのも一つの方法でしょう。
これらの工夫を組み合わせれば、家具家電代を5~10万円以下に抑えることも十分可能です。
生活費はいくらかかる?毎月の支出目安とシミュレーション

同棲をスタートした後に毎月かかる生活費について、具体的な数字とシミュレーションをお伝えしていきます。
二人暮らしの平均生活費データ(家賃除く26~27万円)
総務省が実施した家計調査によると、2024年における2人暮らしの生活費の平均は家賃を除いて268,755円となっています。内訳を見ると次のような構成になっています:
- 食費:75,374円
- 光熱・水道:21,120円
- 交通・通信:35,314円
- その他(被服費・娯楽費・日用品など):約13~14万円
食費は75,374円、光熱・水道は21,120円、交通・通信が35,314円と割合の多くを占めています。特に食費は全体の約3割を占める最大の支出項目です。
家賃を含めた月合計シナリオ(家賃8万・10万・12万)
家賃別の月間生活費シミュレーションは以下の通りです:
- 家賃8万円の場合:約35万円(8万円 + 27万円)
- 家賃10万円の場合:約37万円(10万円 + 27万円)
- 家賃12万円の場合:約39万円(12万円 + 27万円)
ただし、これは全国平均であり、実際の生活費は地域やライフスタイルによって大きく変動します。
節約カップルとゆとり派の生活費比較
二人暮らしの最低生活費(月額)として、節約を重視すれば以下のような構成も可能です:
節約カップルの場合(25万円程度):
- 食費:5万円(自炊中心)
- 光熱費:1.5万円
- 通信費:1万円
- その他:5万円
- 家賃:12万円
一方、ゆとりのある生活を送る場合は35~40万円程度になることも。外食頻度や娯楽費、洋服代などによって大きく変動するため、二人でライフスタイルを話し合っておくことが重要でしょう。
費用分担の決め方|折半・収入割合・項目担当のメリットと注意点

同棲生活において避けて通れないのが、費用分担の決め方です。それぞれの方法について、メリットと注意点をお伝えしていきます。
折半方式のメリット・デメリット
収入に大きな差がない場合、同棲の初期費用は折半することをおすすめします。負担がどちらかに偏ることがないため、あとでトラブルになることを防げます。
折半方式は最もシンプルで公平感のある方法ですが、二人の収入に大きな差がある場合は問題が生じやすくなります。収入の少ない側が経済的に圧迫されるためです。
収入割合方式のメリット・デメリット
二人の収入に応じて、収入が多い方が多く負担する方法です。例えば、二人の収入が30万円と20万円なら、家賃や生活費も3:2の割合で負担します。
この方式なら収入格差があっても公平感を保てる一方で、収入が変動した際の調整や、細かい支出の計算が複雑になりがちという課題もあります。
項目担当方式と実際の分担例
項目ごとに担当を決める方式も人気があります。実際の分担例としては:
- 家賃・光熱費:収入の多い方
- 食費・日用品:収入の少ない方
- 通信費・娯楽費:各自負担
この方式は精神的には楽ですが、項目によって金額差が生まれやすく、結果として不公平感が生じる可能性があります。
不公平感を防ぐための工夫(共同口座・家計アプリ)
円満な関係であり続けるためにも、スタートの段階でつまずかないように、費用の分担方法は明確にしておくことが大切です。
効果的な管理方法として:
- 共同口座の作成:二人専用の口座を作り、決めた金額を毎月入金
- 家計簿アプリの活用:支出の透明性を確保し、お互いが家計状況を把握
- 定期的な見直し:3か月に一度程度、分担方法や金額を再検討
特に共同口座は、口座を作る段階で「予想外の出費があったらこの口座から出そう」などとルールを決めておくと、退去費用が発生したときに揉めにくくなるというメリットもあります。
大切なのは、どの方式を選んでもお互いが納得していることと、状況の変化に応じて柔軟に調整できる仕組みを作っておくことでしょう。
同棲を始める前に知っておきたい”見落としがちな費用とリスク”

同棲には表面的な費用以外にも、見落としがちな出費やリスクが存在します。事前に知っておくことで、後々のトラブルを避けることができるでしょう。
二重家賃や更新料など契約関連の注意点
日割り家賃については、初月の入居日数分が計算されます。たとえば、月の15日に入居する場合は、前家賃とともに家賃の半額が初期費用に加わります。
契約開始日と実際の引越し日がズレると、現在の住居と新居の両方で家賃が発生する「二重家賃」が生じることも。1か月分の家賃が無駄になる可能性があるため、タイミングの調整が重要です。
また、賃貸契約は通常2年更新のため、2年後には更新料(家賃1~2か月分)が発生することも念頭に置いておきましょう。
破局時にかかる金銭リスクと原状回復費用
同棲には別れるリスクも伴います。同棲経験のある男女373人へのアンケートによれば、実際に同棲から別れたカップルの割合は、約4割を占める結果となっています。
破局時に発生する可能性のある費用として:
- 退去費用の負担:クリーニング代は、入居するときに支払った「敷金」から負担されることがほとんどですが、敷金を超える修繕が必要な場合は追加費用が発生
- 家具家電の分配問題:折半して購入した場合、家具家電をどちらが引き取るかで揉めることがあります
- 引越し費用:同棲解消の原因になった相手に費用を請求できるかどうかは、二人が「内縁」や「事実婚」にあったかどうかが重要
同棲解消したあと「これまでの初期費用や家賃、生活費を返して」といわれるケースが少なくありません。基本的に返却の義務はありませんが、相手が別れに納得できないことから、ムリな要求をしてくることもあります。
生活ルール・親への報告など費用以外の心理的ハードル
金銭面以外でも同棲には様々な課題があります:
- 生活ルールの違い:掃除頻度、起床時間、友人の招待など
- 親への報告:同棲を始めることを両親にどう伝えるか
- 将来設計の不一致:結婚のタイミングや子供の希望など
価値観や性格が合わずお別れに至るケースが多く、同棲をして一緒にいる時間が長くなるにつれて、浮き彫りになりやすい部分でもあります。
これらの課題は費用はかからないものの、精神的な負担は大きくなりがち。同棲を始める前に、お互いの価値観や将来の希望についてしっかりと話し合っておくことが、長続きする同棲生活の秘訣といえるでしょう。
まとめ
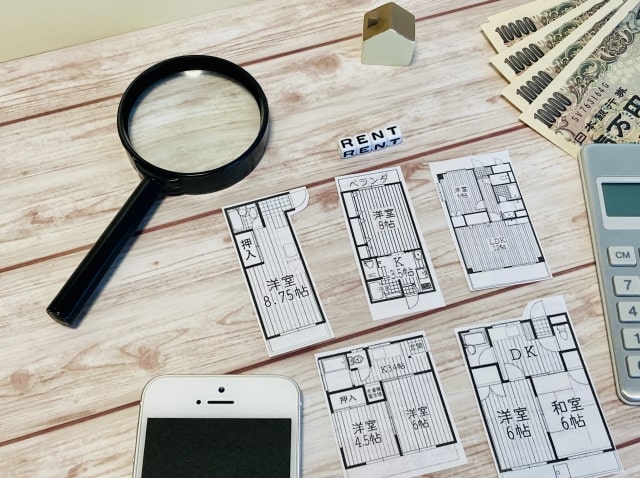
同棲の最低費用について詳しくお伝えしてきました。
標準的には家賃の7~8か月分(100万円程度)が相場とされていますが、工夫次第で50万円台からでも同棲をスタートできることがお分かりいただけたでしょう。敷金礼金ゼロ物件の選択、中古家電の活用、既存の住居を利用するなど、節約方法は数多く存在しています。
毎月の生活費は家賃を含めて35~40万円程度が目安となり、費用分担については折半・収入割合・項目担当の各方式にそれぞれメリットがあります。
同棲を検討されている方へのアドバイスとして、金銭面の計画をしっかり立てることはもちろん大切ですが、それ以上に二人の価値観や将来のビジョンを共有しておくことが重要です。お金の管理方法や生活ルールについて事前に話し合い、お互いが納得できる形で同棲生活をスタートしてみてください!