同棲の平均家賃はいくら?収入別・地域別でわかる適正額と失敗しない家賃設定のコツ
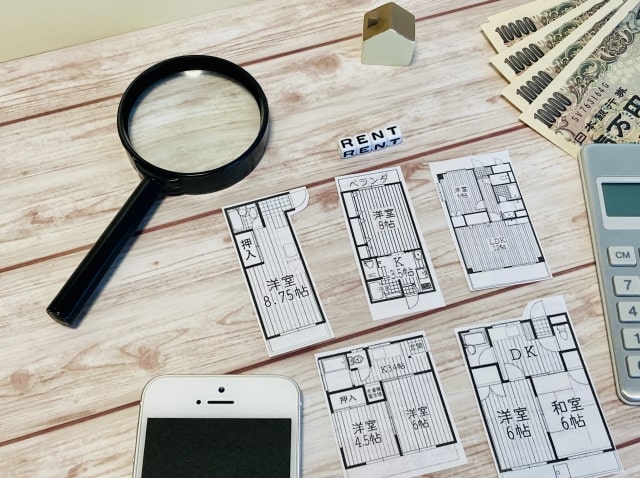
「同棲を始めたいけど、家賃はいくらに設定すればいいんだろう……」
そんな悩みを抱えているカップルは多いのではないでしょうか。
家賃は毎月必ず発生する固定費であり、高すぎると生活が圧迫されますし、安すぎると希望の条件を満たせません。さらに、お互いの収入バランスや将来の貯蓄計画も考慮しなければならず、家賃設定は同棲生活の成功を左右する重要な要素です。
この記事では、収入別・地域別の家賃相場から、無理なく支払える上限額の計算方法、初期費用の内訳、物件選びのポイントまで、同棲の家賃に関するすべてを詳しくお伝えしていきます。
記事を最後まで読むことで、二人にとって最適な家賃設定ができ、快適な同棲生活をスタートできるようになるでしょう!
収入別早見表|同棲カップルが無理なく支払える家賃の上限とは?

同棲を始める際、まず気になるのが「自分たちの収入で、いくらまでの家賃なら無理なく支払えるのか」という点です。
ここでは、収入別に適正な家賃の上限を確認し、生活費全体のバランスについても解説していきます!
家賃は手取りの2〜3割が目安とされる理由
一般的に、家賃は二人の手取り収入合計の2〜3割が目安とされています。
なぜなら、この範囲内に抑えることで、食費や光熱費などの生活費、さらには貯金や娯楽費にも十分な予算を確保できるからです。手取りとは、税金や保険料が引かれた後に実際に使えるお金のこと。この「手元に残るお金」を基準に家賃を考えることが、無理のない生活設計の第一歩となります。
たとえば、手取り30万円のカップルなら6万〜9万円、手取り40万円なら8万〜12万円が目安です。
ただし、将来の結婚資金や緊急時の備えとして貯金を重視したい場合は、手取りの2割程度に抑えることをおすすめします。逆に、立地や設備を優先したい場合は3割まで引き上げることも可能ですが、その場合は他の支出を見直す必要があるでしょう。
合計手取り額から見る上限家賃早見表(20万〜50万円台)
具体的な数字で見ていきましょう。
以下は、二人の手取り収入合計から算出した家賃の目安です。
- 手取り20万円: 4万〜6万円
- 手取り25万円: 5万〜7.5万円
- 手取り30万円: 6万〜9万円
- 手取り35万円: 7万〜10.5万円
- 手取り40万円: 8万〜12万円
- 手取り45万円: 9万〜13.5万円
- 手取り50万円: 10万〜15万円
この早見表を参考に、自分たちの収入状況に合った家賃帯を把握してみてください。
なお、管理費や共益費も含めた「総家賃」で考えることが重要です。物件情報を見る際は、基本家賃だけでなく、管理費や共益費を加えた金額が上記の範囲内に収まっているかを確認しましょう。
家賃を決める前に確認すべき「生活費全体のバランス」
家賃だけを見て物件を決めてしまうと、後で生活費のやりくりに苦労することもあります。
総務省の家計調査によると、二人暮らし世帯の生活費(家賃を除く)は月約26万円とされていますが、同棲カップルの場合は約20〜21万円が現実的な目安です。内訳としては、食費約7万円、水道光熱費約2万円、通信費約1.5万円、交通費約2万円、保険・医療費約1.5万円、娯楽費約3万円、その他雑費約3万円程度となります。
したがって、手取り40万円のカップルが家賃12万円の物件に住む場合、生活費20万円と合わせて32万円。
残り8万円が貯金や予備費に回せる計算です。ただし、奨学金の返済がある、車のローンがあるなど、個別の事情によって変わってくるため、必ず二人で現状の支出を洗い出してから家賃を決めることが大切です!
都市・間取り別の平均家賃相場(東京23区/政令市/郊外)

同じ間取りでも、住むエリアによって家賃は大きく変わります。
ここでは、東京23区をはじめとする主要都市の家賃相場を詳しく見ていきましょう!
東京23区の1LDK・2LDK平均家賃表(区別一覧)
東京23区の家賃は、区によって大きな差があります。
2025年の最新データによると、1LDK・2K・2DKの平均家賃は約13.5万円、2LDK・3K・3DKは約21.8万円です。しかし、これはあくまで平均値。区ごとに見ると、最も安い葛飾区では1LDK・2K・2DKが7.16万円、2LDK・3K・3DKが10.73万円であるのに対し、最も高い港区では1LDK・2K・2DKが29.79万円、2LDK・3K・3DKが63.24万円と、実に約3〜6倍もの開きがあります。
都心3区(千代田区・中央区・港区)や渋谷区は、ビジネス街や商業施設が集中しているため家賃が高め。
一方、足立区、葛飾区、江戸川区などの東部エリアは比較的リーズナブルです。また、練馬区や杉並区などの西部エリアは、都心へのアクセスも良好でありながら、家賃が10万〜12万円台で探せることも多いため、同棲カップルに人気があります。
大阪・名古屋・福岡など主要都市の相場と特徴
東京以外の主要都市では、家賃相場はどうなっているのでしょうか。
大阪市の1LDK・2K・2DKは平均8〜10万円程度、2LDKは11〜14万円程度が相場です。特に梅田や難波などの中心部は高めですが、郊外エリアなら7万円台から見つかることもあります。名古屋市は1LDK・2K・2DKが7〜9万円、2LDKが10〜13万円程度。栄や名古屋駅周辺は高めですが、全体的には東京や大阪より抑えられます。
福岡市は1LDK・2K・2DKが6〜8万円、2LDKが9〜11万円程度。
天神や博多駅周辺でも東京に比べると割安で、コンパクトで暮らしやすい都市として人気があります。いずれの都市も、東京23区と比較すると2〜5割程度安く借りられるため、地方で同棲を始めるカップルにとっては選択肢が広がるでしょう!
郊外・地方エリアで家賃を抑えるコツ(駐車場・通勤時間)
さらに家賃を抑えたいなら、郊外や地方エリアも検討してみましょう。
東京23区外の多摩エリアや、大阪府下、愛知県内の郊外では、1LDKで6〜8万円、2LDKで8〜11万円程度から探すことが可能です。ただし、郊外に住む場合は通勤時間と交通費のバランスを考慮することが重要。片道1時間以上かかる場合、定期代が月2万円以上になることもあり、家賃を抑えた分が交通費で消えてしまうケースもあります。
また、地方エリアでは駐車場代も考慮が必要です。
都市部では月1〜3万円かかることもありますが、地方では無料や月3,000〜5,000円程度の物件も多くあります。車が必須の地域では、駐車場込みの総コストで比較することが大切です。在宅ワークが可能なカップルなら、郊外で広めの物件を選ぶことで、通勤頻度を減らしつつ快適な生活空間を確保できるでしょう!
家賃10〜12万円帯で探す現実的な条件とは?
手取り40万円前後のカップルに人気の家賃10〜12万円帯。
この価格帯で、どのような物件が見つかるのでしょうか。東京23区内なら、葛飾区、江戸川区、足立区、練馬区あたりで1LDK〜2DKが中心。築年数は10〜20年程度、駅徒歩10〜15分の物件が一般的です。都心部で同じ予算だと、築30年以上や駅徒歩20分などの条件になることも。
大阪や名古屋では、この予算があれば市内中心部でも2LDKの築浅物件が見つかります。
福岡なら天神や博多駅周辺でも選択肢が広がるでしょう。条件の優先順位をつけることがポイントです。「駅近」「築浅」「広さ」「設備」のすべてを満たすのは難しいため、二人で話し合って「絶対に譲れない条件」を2〜3つに絞り込みましょう!
家賃の分担モデル3選と”納得できる分け方”の設計方法
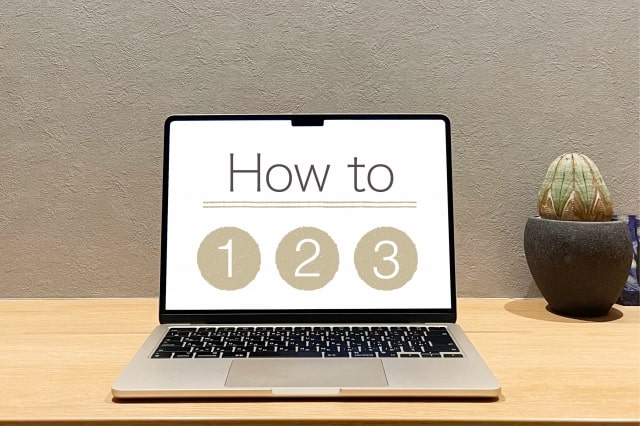
家賃をどう分担するかは、同棲カップルにとって最も揉めやすいポイントの一つです。
ここでは、3つの代表的な分担モデルと、トラブルを防ぐ方法をご紹介していきます!
① 折半方式(最もシンプルだが不公平になりやすいケースも)
折半方式は、家賃を完全に半分ずつ負担する最もシンプルな方法です。
計算が簡単で分かりやすく、お互いの収入が同程度なら公平感もあります。しかし、収入に大きな差がある場合は注意が必要です。たとえば、手取り25万円と15万円のカップルが家賃10万円を折半すると、前者は収入の20%、後者は33%を家賃に充てることになり、生活の余裕度に差が出てしまいます。
このような場合、収入が少ない方が貯金できなかったり、娯楽費を削ったりすることになり、不満が溜まる原因に。
折半方式を選ぶなら、お互いの収入差が10%以内程度であることが理想的です。また、家賃以外の生活費や家事の分担も含めて、総合的にバランスが取れているかを確認することが大切でしょう!
② 収入比例方式(可処分所得で算出する方法)
収入比例方式は、それぞれの手取り収入に応じて家賃を分担する方法です。
たとえば、手取り30万円と20万円のカップルなら、収入比は3:2。家賃12万円を収入比で分けると、7.2万円と4.8万円となります。この方式なら、双方とも手取りの24%を家賃に充てることになり、公平感が保たれやすいでしょう。
さらに精緻に計算したい場合は、可処分所得(手取りから最低限の生活費を引いた自由に使えるお金)で比率を決める方法もあります。
ただし、一方が家事の大半を担っている場合や、片方だけが在宅勤務で光熱費がかさむ場合など、金銭以外の貢献度も考慮することが重要です。収入比例方式を採用する際は、家事や生活費の分担も含めて、総合的に納得できる仕組みを作りましょう!
③ 費目別分担方式(家賃と生活費を分けて支払うパターン)
費目別分担方式は、「家賃は〇〇さん、生活費は△△さん」というように、項目ごとに担当を決める方法です。
たとえば、収入が多い方が家賃10万円を全額負担し、収入が少ない方が食費・光熱費・日用品費などの生活費8万円を負担するパターン。この方式のメリットは、それぞれの責任範囲が明確になり、お金の管理がしやすい点です。
ただし、生活費は変動するため、「今月は食費が高かった」などの調整が必要になることも。
また、一方が固定費、もう一方が変動費を担当する場合、毎月の負担額に差が出やすいため、定期的に見直すことが大切です。この方式を選ぶなら、3ヶ月に一度など定期的に収支を確認し、不公平感が生じていないかチェックしていきましょう!
トラブルを防ぐ!合意書・共有口座の使い方
どの分担方式を選んでも、口頭での約束だけでは後々トラブルになる可能性があります。
そこでおすすめなのが、家賃や生活費の分担ルールを文書化した「合意書」を作ること。法的な効力を持たせる必要はありませんが、「家賃は収入比3:2で分担」「光熱費は折半」など、決めたルールを書面に残しておくことで、認識のズレを防げます。
また、共有口座を作るのも有効な方法です。
毎月決まった金額を二人で共有口座に入金し、そこから家賃や光熱費を引き落とすようにすれば、お金の流れが透明化され、「ちゃんと払ってるの?」といった疑念も生まれにくくなります。ただし、共有口座は解約や名義変更が面倒なケースもあるため、同棲解消時のルールも事前に決めておくことが重要です!
初期費用の内訳と節約テクニック:引越し・敷礼・保証料 他

同棲を始める際、家賃だけでなく初期費用も大きな負担となります。
ここでは、初期費用の詳しい内訳と、賢く節約する方法をお伝えしていきます!
初期費用の総額は家賃◯ヶ月分?内訳と計算式
賃貸物件の初期費用は、一般的に家賃の4.5〜6ヶ月分が相場とされています。
家賃10万円の物件なら45〜60万円が目安です。具体的な内訳を見ていきましょう。敷金は家賃1〜2ヶ月分(10〜20万円)で、退去時の原状回復費用に充てられます。礼金も家賃1〜2ヶ月分(10〜20万円)で、大家さんへのお礼として支払う費用。前家賃は家賃1ヶ月分(10万円)で、翌月分の家賃を契約時に前払いします。
日割り家賃は入居日によって変動しますが、月半ばなら0.5ヶ月分程度(5万円)。
仲介手数料は家賃1ヶ月分+税(11万円)が上限です。火災保険料は1.5〜2万円、鍵交換費用は1〜3万円、保証会社利用料は家賃0.5〜1ヶ月分(5〜10万円)程度。これらを合計すると、家賃10万円の場合、概算で52〜76万円となります。物件によっては、さらにハウスクリーニング費や消毒費がかかることもあるため、余裕を持って準備しておきましょう!
引越し時期による費用差(繁忙期・閑散期の違い)
引越し費用は、時期によって大きく変動します。
3〜4月、9〜10月の繁忙期は、進学や転勤シーズンで需要が高まるため、引越し料金が平常時の1.5〜2倍になることも珍しくありません。逆に、5〜8月、11〜2月の閑散期なら、同じ引越しでも3〜5割程度安くなる場合があります。
また、繁忙期には家賃交渉が難しくなる一方、閑散期なら敷金・礼金の値下げ交渉に応じてもらえる可能性も高まります。
タイミングを選べるなら、5月以降や11〜12月に引越しを計画することで、初期費用全体を大幅に削減できるでしょう。さらに、月末よりも月初に入居すれば日割り家賃を抑えられ、前家賃が不要になるケースもあります。引越し業者の見積もりも、平日や午後便を選ぶことで安くなることが多いため、工夫次第で節約可能です!
フリーレント・敷金礼金ゼロ物件の注意点
初期費用を抑える手段として、フリーレントや敷金礼金ゼロ物件は魅力的に見えます。
フリーレントとは、入居後1〜3ヶ月の家賃が無料になる契約のこと。しかし、多くの場合「〇年以内の解約は違約金発生」という条件が付いているため、短期で引っ越す可能性がある場合は注意が必要です。また、フリーレント期間中も管理費や光熱費は発生するため、完全にタダというわけではありません。
敷金礼金ゼロ物件も、一見お得に見えますが、別の形で費用が上乗せされているケースがあります。
たとえば、ハウスクリーニング費や消毒費が高額に設定されていたり、退去時のクリーニング代が契約書の特約で定められていたり。さらに、敷金がない分、退去時の原状回復費用を全額請求される可能性もあるため、契約前に重要事項説明書をよく確認することが大切です!
家具・家電の買い替えコストを抑える工夫
同棲を始めると、二人分の家具や家電を揃える必要が出てきます。
ベッド、テーブル、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど、一から揃えると30〜50万円かかることも。しかし、工夫次第で大幅にコストダウンできます。まず、一人暮らしで使っていた家電をそのまま活用しましょう。冷蔵庫や洗濯機は、小さめでも最初は十分使えます。
また、リサイクルショップやフリマアプリを活用すれば、状態の良い中古品を新品の半額以下で購入可能です。
家電量販店の新生活応援セットも、単品で買うより割安になることが多いため、チェックしてみましょう。さらに、実家から使わなくなった家具を譲ってもらうのも手です。すべてを一度に揃えようとせず、「最低限必要なもの」を先に用意し、余裕ができてから買い足していくスタイルなら、初期負担を大きく軽減できます!
物件選びのチェックリスト:駅距離・築年・設備・騒音・契約条項

家賃や初期費用が決まったら、次は実際の物件選びです。
ここでは、同棲向き物件を見極めるためのチェックポイントを詳しく解説していきます!
同棲向き物件の条件とは?理想と現実のバランス
同棲向き物件を選ぶ際、多くのカップルが「駅近」「築浅」「広い」「設備充実」を求めます。
しかし、すべてを満たす物件は家賃が高額になりがち。そこで重要なのが、理想と現実のバランスです。まず、二人で「絶対に譲れない条件」を2〜3つ決めましょう。たとえば、通勤を重視するなら「駅徒歩10分以内」、在宅勤務が多いなら「日当たり良好・静かな環境」、料理好きなら「広めのキッチン」など。
逆に、優先度が低い条件は妥協することで、予算内に収まる物件が見つかりやすくなります。
築年数は新しい方が設備も整っていますが、築15〜20年でもリノベーション済みなら快適に暮らせることも。駅から少し離れても、バス便が充実していれば不便さを感じにくい場合もあります。理想を100%求めず、80点の物件を見つける意識で探すことが、満足度の高い同棲生活につながるでしょう!
在宅勤務・二人暮らしに必要な広さと間取りの考え方
同棲の間取りは、1LDK、2DK、2LDKが人気です。
1LDKは常に一緒に過ごしたいカップル向けで、家賃も抑えやすいのがメリット。ただし、生活リズムが異なる場合やリモートワークで会議が多い場合は、音や気配が気になることも。2DKは、リビングスペースと独立した部屋が二つある間取りで、お互いの時間を確保しやすい反面、リビングがやや狭めです。
2LDKは広々としたリビングと二つの個室があり、理想的ですが家賃は高めになります。
在宅勤務が多い場合は、最低でも2DK以上を選ぶことをおすすめします。一方が仕事中にもう一方がリラックスできるスペースがないと、ストレスが溜まりやすいからです。また、広さの目安としては、二人暮らしなら40〜50㎡あれば快適に過ごせるでしょう。収納スペースも重要なポイントです。クローゼットが小さいと、部屋に物が溢れて狭く感じてしまうため、内見時にしっかり確認しましょう!
内見時に必ず確認したいポイント(通気・日当たり・水回り)
内見は、写真だけでは分からない情報を得る貴重な機会です。
まず、日当たりをチェックしましょう。南向きが理想ですが、東向きでも午前中は明るく、西向きは午後から夕方にかけて日が入ります。北向きは日当たりが悪いため、湿気やカビに注意が必要です。次に通気性を確認。窓の位置が対角線上にあれば風が通りやすく、一方向だけだと空気がこもりがちになります。
水回りは特に念入りにチェックしてください。
キッチンは二人で料理する場合、作業スペースやシンクの広さが重要です。お風呂は追い焚き機能の有無、トイレはウォシュレット付きかどうかなど、毎日使う場所だからこそ妥協しないことが大切。また、実際に水を流してみて、水圧や排水の状態も確認しましょう。騒音チェックも忘れずに。壁を軽く叩いて響き具合を確かめたり、隣の部屋の音が聞こえないか耳を澄ませてみたりすることも有効です!
契約書で見落としがちな項目(更新料・違約金・原状回復)
契約書には、後々トラブルになりやすい重要事項が記載されています。
まず、更新料の有無と金額を確認しましょう。関東では家賃1ヶ月分が一般的ですが、大阪や名古屋では更新料なしの物件も多くあります。2年ごとに10〜15万円の出費となるため、長く住む予定なら事前に把握しておくことが重要です。次に、途中解約時の違約金。通常は1〜2ヶ月前の解約予告で違約金は発生しませんが、「1年以内の解約は家賃1ヶ月分の違約金」などの特約がある場合も。
特に、フリーレント物件では短期解約の違約金が高額に設定されていることが多いため要注意です。
原状回復についても、契約書の特約をしっかり読んでください。「退去時のクリーニング代は借主負担」「畳の表替え費用は借主負担」など、通常の原状回復ルールを超える負担が定められている場合があります。国土交通省のガイドラインでは、経年劣化や通常損耗は貸主負担とされていますが、特約で借主負担となっているケースもあるため、納得できない条項があれば契約前に交渉してみましょう!
同棲後の”中長期コスト”と解消時リスク:更新料・原状回復・退出費用 など

同棲をスタートする時だけでなく、その後のコストや万が一の解消時リスクも考えておく必要があります。
ここでは、中長期的な視点でかかる費用について解説していきます!
2年後に発生する更新料・再契約費用の目安
賃貸契約は2年ごとの更新が一般的で、その際に更新料が発生します。
関東では家賃1ヶ月分(10万円の物件なら10万円)が相場ですが、地域や物件によって異なります。京都では家賃2ヶ月分になることもある一方、大阪や名古屋、中国・九州地方では更新料なしの物件が主流です。更新料に加えて、火災保険の更新料(1〜2万円)、保証会社の更新料(1万円程度または家賃の10〜30%)も同時に発生することが多いでしょう。
つまり、家賃10万円の関東の物件なら、2年ごとに12〜15万円程度の出費を見込む必要があります。
この費用を急に用意するのは大変なので、毎月5,000〜6,000円ずつ積み立てておくと安心です。また、更新料の支払いが難しい場合は、分割払いに応じてもらえるケースもあるため、早めに管理会社に相談してみましょう。更新のタイミングは、住み続けるか引っ越すかを見直す良い機会でもあります!
退去時にかかる原状回復・クリーニング費用の相場
退去時には、原状回復費用とクリーニング費用がかかります。
敷金を払っている場合は、そこから差し引かれて残額が返還されますが、敷金なし物件では全額負担となるため注意が必要です。クリーニング費用は、1LDKで3〜5万円、2LDKで5〜8万円程度が相場。原状回復費用は、故意や過失による損傷があれば追加でかかります。たとえば、タバコのヤニによる壁紙の変色は借主負担となり、1LDKで5〜10万円程度。
ペット可物件でペットによる傷や臭いがあれば、さらに高額になることも。
一方、日照による床の色褪せや、家具を置いたことによる床のへこみ(経年劣化)は、通常は貸主負担です。ただし、居住年数によって借主の負担割合が変わります。たとえば、壁紙の耐用年数は6年とされており、2年居住した場合、残存価値の約66%が借主負担の目安となります。敷金2ヶ月分(20万円)を預けていても、原状回復費用が25万円なら5万円の追加請求となるため、退去時の出費も見越しておきましょう!
同棲解消時にトラブルを防ぐための名義・契約管理のポイント
残念ながら同棲を解消することになった場合、お金や契約に関するトラブルが発生しやすくなります。
最も重要なのが、賃貸契約の名義です。通常、契約者は一人だけで、もう一方は「同居人」という扱いになります。契約者が退去を決めた場合、同居人は住み続けることができません。逆に、同居人だけが退去したい場合でも、契約者の同意なしには解約できないのです。
このような事態を避けるため、同棲を始める前に「解消時のルール」を二人で話し合っておきましょう。
「どちらかが出ていく場合、家賃や初期費用の精算はどうするか」「家具や家電の所有権はどうするか」など、細かく決めておくことが大切です。また、共有口座を作っている場合は、解消時の残高をどう分けるかも明確に。家賃の分担で片方が多く払っていた場合、敷金の返還分もその比率で分けるのが公平でしょう。感情的になりやすい時期だからこそ、事前の取り決めが冷静な解決につながります!
まとめ

同棲の家賃設定は、二人の収入や将来の計画を踏まえて慎重に決めることが重要です。
手取りの2〜3割を目安に、生活費や貯金とのバランスを考えながら、無理のない範囲で物件を選びましょう。東京23区なら10〜13万円台、大阪や名古屋なら8〜11万円台、福岡なら7〜10万円台が同棲カップルに人気の価格帯です。家賃の分担方法は、折半・収入比例・費目別分担の3つが代表的ですが、どの方式を選ぶにしても、お互いが納得できるルールを作ることが大切。
初期費用は家賃の4.5〜6ヶ月分を見込み、閑散期の引越しやフリーレント物件の活用で節約できます。
物件選びでは、駅距離・築年数・設備・日当たりなどの優先順位を明確にし、内見時には水回りや騒音もしっかりチェックしてください。また、2年ごとの更新料や退去時の原状回復費用など、中長期的なコストも把握しておきましょう。万が一の同棲解消に備えて、契約名義や費用分担のルールを事前に決めておくことも忘れずに。
これらのポイントを押さえて、二人にとって最適な家賃設定と物件を見つけ、素敵な同棲生活をスタートさせてください!